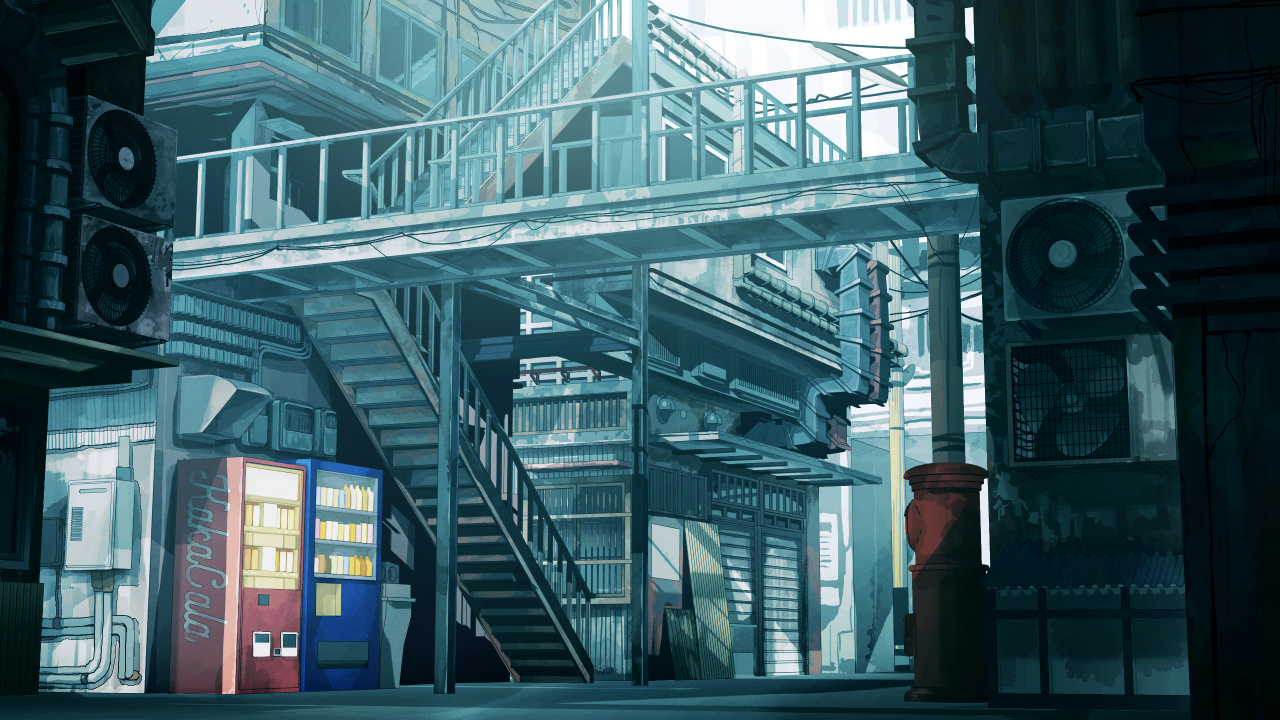√ラ・セスタ・カンチェッラータ『メナシトカゲ』
●√
希望は美しいものだと思う。
「だって、当然じゃあないですか」
大層に美しいものだと知ってはいるが、私はどうしても首を傾げてしまうのだ。
希望とは美しいが、そんなに得難いものなのだろうか、と。
人類は黄昏を迎えている。
進化は止まり、慢性的な疲労と倦怠とが人類を苛んでいる。
薄暮のようにヴェールが視界にも心にも掛かっているような気がしてならない。
希望は太陽のように燦然と輝くから美しいとも言える。
けれど、今現在の人類が保ち得ているのはイカロスの翼だ。
近づけば、溶けて落ちる蝋の翼でしかない。
「だから、希望を歌うのは辞めて欲しいって話ですか? いやです。そんなのいやです。絶対にいやです」
白い髪が揺れて、すみれ色の瞳が潤むようだった。
見れば見るほど普通の少女だ。
多感な時期には、私もこうだったのかもしれないと思う程度には普通の少女だった。
普通の少女らしく、麻疹のように社会というものに対して背伸びをして斜めに物事を見たがる時期に差し掛かっている特有の気配を感じさせていた。
思春期と言えば、その通りなのだろう。
とは言っても私の頃とは時代も文明も技術というものが違う。
目の前の少女は、『Vsinger』というものらしい。
所謂、動画投稿サイトへと動画を投稿する配信者と言えばいいだろうか。ただし、実際の自分の姿ではなく、2DCGだかなんだかよくわからないキャラクター……この場合はアバターというのが正しいのだろうか。
それを用いた動画投稿なのだと彼女は力説していた。
私は幸いにというか、不幸というか。
自身のそうした心の内を発露する機会を逸したまま、どこかに置き忘れてきたし、ただ徒に傷を作るばかりであった。
時折、彼女のような少女を見ると塞がったと思った傷跡が痂でしかなかったのだと気がついてじくじくと痛むのだ。
「ええと、ア……ラ、さん? この名義で投稿されたあなたの」
「『アーラ』、『A』、『L』、『A』で『Ala』です」
「失礼。あなたが投稿された動画が問題なのです」
私は言葉を慎重に選ぶようになっていた。
目の前にいるのはただの少女に見えるが、人間の形をしているだけの存在に過ぎないことを思い出したのだ。
おかしい。
私は汎神解剖機関の職員である。
こうした怪異に準じる事柄に関してはいくつかの経験を得ている。問題は、それが時としてまったくもって役に立たない、ということである。
目の前の少女も、その役に立たない部類に入る。
一瞬でも彼女と少女時代の自分を重ねてしまっていたのは、一体如何なる理由からか私は判然としない。
「何が問題だって言うんですか! だって、わたし、ただ歌って動画を投稿しただけですよ!?」
「問題なのは」
「わたしがこの歌声で塞ぎ込んだみんなの、インターネット・エンジェリック・ディーヴァになってあげる! それだけなんですよ!」
「インターネット、え、なに?」
「インターネット・エンジェリック・ディーヴァです」
わからない。
世代が違うとかではない。
文化そのものが違うとしか言いようがない。
少しでも親近感を覚えた自分が恥ずかしい。
「話を戻しましょう」
「はい」
「あなたの投稿した動画……確かに歌を歌っていますね」
「そうです! 新曲だって、作曲して! 作ったんです! え、もしかして聞いてくださっていたり!」
しますか、と彼女のすみれ色の瞳が爛々としているのを見て、気が滅入る。
「聞きました。聞きましたが」
「どうでしたどうでした!」
「頭がクラクラしました」
「そんな! わたしの歌声にクラクラしちゃうほどにメロメロだなんて!」
「メロメロとまでは言っていません。ですが、一部の被験者には、貴女を信奉するような言動を発する者もいれば、酩酊状態のように多幸感を覚えた者もいました」
私は、これを一種の『洗脳』ではないかと疑っていた。
そんなことが起こり得るだろうか?
もしも、だ。
彼女が、その力で何かを扇動した時、これに抵抗できる者がいるのだろうか?
これまでの実験結果から見ても彼女の歌声は『依存』、『酩酊』、『洗脳』といった効果を齎すことが確認されている。
つまり、彼女は人間の意識を乗っ取ることのできる声ないし能力を持つ可能性がある。
彼女自身にそのつもりがなくとも、彼女の能力に目をつけたものが『悪用』を企てた時、誰がこれを止められるだろうか?
止められない。
彼女が人類の死を願ったのなら。
動画投稿サイトに、その歌声で願ったのなら。
――それはきっと叶ってしまう。
確実に人類社会を崩壊させ得る可能性を内包した存在であることは言うまでもない。
そこまで考えて私は理解した。
こうして彼女と対面で会話している内に、心が解かれている気がする。言い方を変えれば、絆され始めている。
確かに、彼女の能力は恐るべきものだ。
悪用されれば一大事だ。
駄目だ。
問題が単純化されていくようだ。
私自身、それを止められない。意識しても、彼女の言葉を、声を聞いている内に彼女の言い分の通りだと思うようになっている。
「わたし、希望を歌いたいんです! だって、こんな世の中じゃあないですか! 暗がりを照らすような光があった方がいいんです。どうせみんなお先真っ暗なんですから、足元くらい照らしたいじゃあないですか!」
わかる気がする。
世界は薄暮のような暗がりに満ちている。
怪異はそこかしこにはびこっている。
此方を非日常に引きずり込もうと虎視眈々と闇の中から伺っている。それを知ったあの日から私の心は、狂気と不安と恐怖とで擦り切れそうだった。
事実、これが彼女の年頃に望んだ非日常だということは理解している。
だが、願うのと実感するのとでは意味が違う。
世の中の真というものは、もっとずっと複雑怪奇で誰にも制御などできないのだ。
知らぬ間に通り魔に傷つけられても、己が身から血潮が流れていることにすら気づけぬままに生きていかねばならないのだ。
生きる事は死ぬこと。
希望に向かうことは絶望を知ること。
そんなこと、誰も教えてはくれないのだ。
泣いても涙を拭う者はいない。すがっても、素気なく振り払うだけなのだ。
「わかりますよ。不安ですもんね。見通しの効かない先のことなんて考えていたくないですよね」
少女の高い声が慈愛に満ちているように思えてならなかった。
「だから、わたし、歌うんです。希望を。だから、人間災厄だなんて、心外です!」
「それは」
「そうでしょう? 歌っているだけなんです! これからもそうですよ!」
「……なら、そうなのでしょう、ね。ええ」
「そうですよ! だから、ね」
「はい」
私はレポートに記す。
タブレットを操作する。
報告書。
人間災厄指定・脅威度C-。
仮称『小夜鳴鳥』
本件に関して、インターネット上にて散見されたアカウント名『Ala』の動画に関するコメントは、人間災厄の能力に寄るものであると断定できる。
しかし、その脅威度は低いと判断されるものである。
向精神的作用のみに焦点を絞れば、むしろ有用であるとも判断できる。
また、仮称『小夜鳴鳥』の性質から考えても、人類社会を脅かす程度は低い。
収容ではなく、監視に切り替えて対応すべきである。
また、肉体的な拘束も不要である。
「ああ!『Ala』ちゃんの歌を聴くと元気が出ます!! 本当なんです――」
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔴🔴🔴🔴🔴🔴 成功