わだつみのブルー・ムーン
●月下のクロリス
くるしいほどに光るあおいろが、そらと交わるかの如く望洋と続いている。近付けば白い縞を不規則に描いた波が痺れたようにさわさわと泡を立てながら揺らめいた。
空に、海に。月が満ちている。星の光を乱反射して水面を幾重にも割りながら、海は静かに、確かにそこに広がっていた。
「どこまでも、どこまでも。あおい、あおい……そらとうみが交わる境界線に、手を伸ばしてみたいと思ったことはない?」
ぎこちなく体を硬くして、声を上擦らせながら問い掛ける。この場に集まってくれた能力者たちの顔をひとりひとり確認するように視線を巡らせ、けれども直ぐに頬に朱をのぼらせてゲルダ・ドレッセル(烏夜・h06809)は『えっと』と歯切れの悪い言葉をもごもごと口内で籠らせた。
「きょう、みんなを呼んだのはね。その……そんなあおいろのせかいに、おまねきしたいなって思ったからなの」
人見知りであるらしい彼女がそれでも搾り出したのは、竜の血を継ぐものたちが挑んだ絶海に伝わるひとつの物語であった。
ルーナサの収穫祭がはじまるよりも前。
欠けて、満ちて。七つの月が再び満ちるとき、青の扉は開かれる。
慈しみ深き母よ、憐れみ幽き父よ。今宵、我らが罪を赦しましょう。
その胸に。ねがいが、いのりがあるならば。みなそこに満ちる月に、想いを告げてご覧なさい。そうすればきっと、その想いはかたちになるはずだから――。
クロリス。それは忘れられた孤島に咲く花。
ひとの手が全く入らないその島に、一年に一度だけ。七つの月が満ちるこの夜にだけ、一斉にそのあおい花は咲くのだと言う。
「その花の蜜をひとくち含んだなら、ひとも魔物も、かみさまも……みんながみんな、水の中で自由に動けるようになるの。ふしぎだよね」
生まれも育ちも、種を違えようと。その花の蜜を口にしたなら、あおいろの境界線に足を踏み入れることが出来る。青の扉とはその名の通り、どこまでも広がる青い海のふちを指す言葉なのだろう。クロリスの祝福を得られたものは水の中も自由自在に動くことが叶い、呼吸や会話も問題なく行えるようになる。もちろん水圧でぺしゃんこになってしまう心配はない――とは言え花が枯れてしまえばその効力を失ってしまうから、ほんとうに一夜限りの魔法でしかないのだけれど。
「泳げなくても、立派なエラやヒレがなくっても。みんなはうみのなかを自由にあるけるんだよ」
煌めく夜の海の中をただ歩むだけでも常は見られぬ光景を胸に刻むことが叶うだろう。それに、とゲルダは不器用に微笑みながら言葉を続けた。
「海のおくふかく。みなそこのいちばん奥深くに、月が満ちているんだって」
それは人々の夢の残滓。
揺蕩うひかりが描き出した時の移ろい。難破船の航海者が見た、月の面影。
「もし、そのすがたをみることができたなら。みんなは『みたかったもの、あいたかったひと』に、また会える」
失くしたかけら。足りないかけら。あなたのこころに出来た『うつろ』を、月はきっとひとときのあいだだけ満たしてくれるはずだから。
「青の扉を、潜ってみて。きっと……すてきな夜になるはずだから」
潮騒が聞こえる。
停泊していた船の汽笛が、一際高く周囲に響いた。
第1章 日常 『花咲く世界』
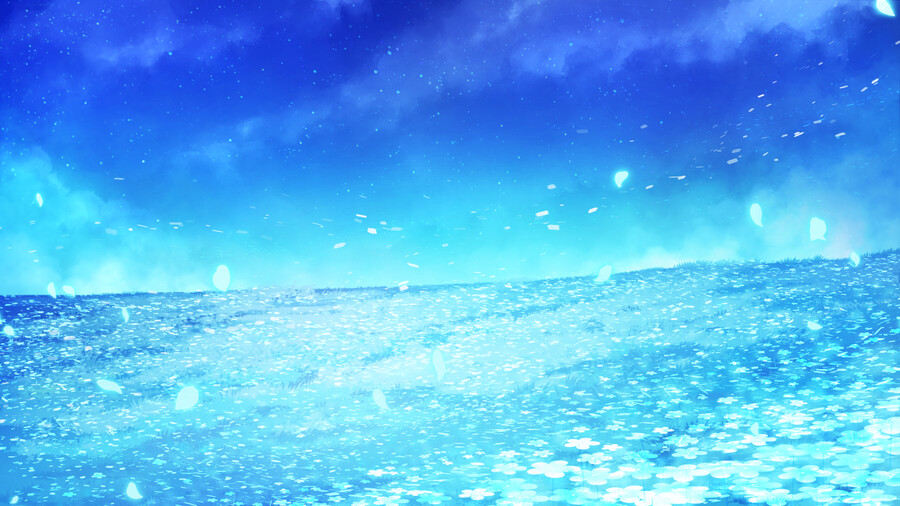
●きみのねがい
夏霞越しの青空をのしたようなあおいろが夢の中から香り出したかのように咲いている。ニゲラの花によく似たかたちをしているが、それよりももっとずっと、それらは鮮烈ないろのように感じられた。
あまく薫るその花は女神が溢した涙なのだと誰かが言った。
一年に一度、たった一晩の間だけ咲くその花々は毛氈の如く広がって、胸いっぱいに空気を吸い込めばそれだけで夢に誘われていくかのようだった。
月が、星が満ちるそらが、手を伸ばせば届きそうなほどに近く感じる。
時の流れがひどく緩やかに進むこの場所で、あなたは何を願うのだろうか――。
●あまいあまつぶ
一年に一度きり。それはなんて特別な夜なのだろう。
タラップから爪先を伸ばした懐音・るい(明葬筺・h07383)は期待に弾む|■《胸》の鼓動をそのままに、視界いっぱいに広がる花々を踏み締めぬようにそろりと身を委ねて。あまい香りを乗せながら受け止めてくれたやわらかな地面に、ほう、と夢みがちな吐息を溢した。
「綺麗」
その花は可憐に咲き誇り、漣を連れるかのように風に戯れながらうつくしいあおいろを宵の空へと伸ばしていた。導く先は遥か続く青の彼方。その切符がこの一面に広がる花の蜜なのだ云うのもるいの幼心と好奇心をたいそう擽ってくる。
「(あと、その先で……会いたい人にまた会えるっていうのも)」
この身はひとにあらず。それでもこのうつろはあの人を望んでやまない。もう一度、今一度。そんなの、こんなの、まるで――■■みたいだ、なんて。
「……ふ」
唇から微かに溢れたのは自分に向けたものだったのか、それとも。
あおく、あおく。どこまでも広がる花の絨毯を傷付けぬように歩を進め、淡い涙花の双眸をあまく撓めて、るいは緩くかぶりを振ると仄暗い感情めいた靄を振り払う。今はただ、このどこまでもうつくしいあおいろに浸っていたかったから。
「この花って何か作って残せたりしないのかなぁ」
たった一夜だけのものだからこその価値があるのかもしれないけれど、それでも夜が明けて仕舞えば枯れてしまうのは少し寂しいなと脳裏に過らせながら、るいはそうとクロリスの花のひとつにゆびさきを伸ばす。軽く捻れば容易く花はてのひらの中に収まって、口に含めば溢れた蜜はするりとほどけながら喉奥に落ちていくようで。甘いけれど華やかで、かといってくどさがあるわけではない。
「ん、すごく美味しい」
凡そ今まで口にしてきたどの甘露とも異なり、それでいて『そのつぎ』を誘うに丁度いいひと雫で喉を潤してくれる。成る程、これは確かに虜になってしまう者が後を立たないという噂も分かるかも、なんて。るいは柔く綻びながら、暫し風に揺れるクロリスの花と海の境界線をじっと見詰めていた。
●ブルー・パレット
名もなきこの島を求めた船が、一縷の望みに縋って再会を望んだ旅人がどれほどこの地に辿り着けたのだろうか。
「やっぱり……この世界、大好きだなあ」
視界を埋め尽くす一面の青。竜の血を継ぐ者達が紡ぐ青はどこまでも澄み切っていて、息を呑むほどにうつくしい。アンジュ・ペティーユ(ないものねだり・h07189)は万感の思いを音にしながら大きく息を吸い、臓腑いっぱいに涼やかな夜の空気を満たしてうんとひとつ伸びをした。
「(あの日も確か、こんなふうに真っ青な花が咲いていたっけ)」
海の青。空の青。
あの日みた花は真昼の好天を知る子たちだったけれど、今宵は夜の天蓋の中だけで生きる花だ。星々の煌めくそらの下に腰を落ち着けながらクロリスの花を見つめれば、ぼうと星明かりに照らされた花自体が淡く光っているようにも見えた。
「いい景色」
たまらず溢れ落ちた呟きは心からのもの。甘い蜜をいっぱいに蓄えた花の香りに酔い痴れたなら、不思議とこころもやわくまろみを帯びていくような心地がする。
一輪だけ手折った花を好奇心のままに唇に寄せたなら、口いっぱいに広がる芳醇な甘味が一瞬、ほんの一瞬だけこの世のいやなこと全てを忘れさせてくれるかのような甘美な心地を連れてくるものだから。アンジュはふわぁ、と吐息を溢して緩みそうになる頬をてのひらで抑えて目を細めた。
「んー……! 確かにこれは、虜になる味だ……!」
この味の再現が出来るようになればこの世界にさいわいの恩返しも出来ようものではないか、なんてぱっと頭の中に思い浮かぶけれど。
「……ううん、違うな」
一年で一度だけ。今宵、この瞬間、ここでしか見ることが出来ない景色。この夜にしか味わうことのできない|甘露《感情》。その全てが揃った特別なものだからこそ価値があるのだと、少女はふっと笑みを深める。
「だからあたしは、この場所を再現するのではなく、語り継ぐことをしようかな」
伝説はほんとうだったのだと。
奇跡は誰しもが触れ得るところに確かに存在するのだと――いとしいこの世界に住まう人々が、のぞめるように。
●なみだとしずく
「うわ、すっげ……世界が全部真っ青だ」
慣れぬ船旅の先に広がるあおいろに目を瞠り、水無瀬・祈(五月雨・h06808)はその歩みで花を傷付けてしまわぬようにそろりそろりと常の何倍も慎重に靴先を運ぶ。まるで海か空に放り出された気分だと、胸に湧いた感情が波紋が広がるかのように震えているのを感じていた。
こわいことはありはしないのだと聞いてはいたけれど、念の為と佩いた二振りの刀が酷く無粋に感じるほどに、忘れられた蒼き孤島は祈を静かに優しく受け入れてくれた。
青は好きだ。
綺麗だし、何より好きなひとの色だから。
この花は女神の溢した涙なのだと、今は港で待つ彼女は言っていた。
この島が人々から忘れ去られたことを憂いたのだろうか、それとも。こんなに、これほど。島を埋め尽くすほどに、悲しいことがあったのだろうか。
「今は……泣いてないといいけど」
水無瀬の跡を継ぐと決めた理由は使命感も勿論あるけれど、恐らくその根本は人々を怪異から救う両親への憧れもあったように思う。だからこそ、祈は女神の憂いが晴れていればいいと願わずにはいられなかった。
怪異が齎す不幸を、悲劇を、ひとつでも減らしたい。困っている人たちを両親のように助けるんだと胸に誓った。自分が最後の水無瀬の生き残りとなってしまった今でもたったひとつの大切なものは変わっていない。
「(俺にはそれしかないから)」
花が湛えた蜜をそっと一口含む。本当ならこの景色を共にしたかった貴女に、せめても思い出をたくさん連れて帰りたかったから。
「……うっま!」
日曜日のパンケーキより甘くて、鍛錬の後のレモンシロップよりじんわりと沁みる。ああ、でも――俺はそっちの方が好きだな、なんて。いくつも浮かんだやさしい面影たちを思い起こして、堪らず祈はふは、と吐息だけで笑った。
「こんなに静かな気分、いつ以来だろな」
波が寄せて返す音に混じり、風と共に花の微かな囁きが耳にすっと溶けては消えていく。そこには怒りも悲しみもない、ただ透明な感情だけが心地よく満ちていた。
●いつくしみぶかき
遠く、遠く。遥か彼方まで。一色しかない絵の具のチューブでかみさまが絵を描いたみたいだ。雨に染まる双眸にきらきらと星明かりを宿して、天深夜・慈雨(降り紡ぐ・h07194)は花の水面を滑るように爪先を踊らせた。
「クロリスのお花……すごいいっぱい、とってもきれー!」
島の表面が真っ青に染まって月のひかりを受けてちかちかと煌めいている。波が押し寄せている訳ではないのに、まるでこの島までもが海とひとつになったかのようだった。
心地よく頬を撫でる風が踊るたび、戯れ合う花々がさわさわとまるで声を立てているよう。内緒話をしているのかな、なんて耳を寄せてみたなら花弁のひとつが慈雨の頬を優しく擽るものだから。きゃあ、と少女の唇から弾む声が溢れて、直ぐにおはなしの仲間入りをしたような気持ちになって膝を折って屈み直すとクロリスの花々をまじと見詰めた。
「『おはよう』ってみんなしてるのかなぁ」
一夜限りの目覚めの魔法に、一年分の『あのね』を乗せて囁き合っているのかも。まあるく浮かんだお月さまだって、きっと一晩中みていたいんじゃないかって。そんな風に思えば花を手折ってしまうことは気後れしてしまうけれど。
「ごめんね」
宙で一瞬彷徨わせたあと、そっと。あおい花を一輪手に取って蜜を口に含む。
「……ゆめに描いたシロップみたい」
いくらでも口にしたくなるくらいに甘美な味わいだというのに、どうしてだろう。すこしだけ胸の奥がきゅうと締め付けられるような切なさを連れてくるのは。
花の海の続きを描くように広がる水平線を見詰め、蜜をくれたクロリスをやさしく両の手に抱いて。慈雨はまるでそこにいのちがあるかのように柔く目を細めてあおい花へと語り掛ける。
「あの青の扉の先にはね。一面のあおとお月さまがあるんだって」
おともだちといっしょに、月をみていたかったよね。
ごめんね。ありがとう。――だから。
「あなたも慈雨と一緒にそこまでいこう」
あなたが行くことのできなかったみなそこで。あなたたちが一番あいした、うつくしい月を共に見るために。
●きみと駆ける
さく、さく、と。不揃いな足音はひとのそれよりも多く、軽く、花々を傷付けぬよう歩むことに長けていた。夜闇に溶けてしまいそうなほどのうつくしい毛並みを持つ気高き天馬。それは月夜見・洸惺(北極星・h00065)の本来のすがたに他ならない。
「夜空のあおもお花畑のあおも、どっちも幻想的でとっても綺麗だねっ」
八つの蹄を鳴らしながらその背に乗せた集真藍・命璃(生命の理・h04610)を降り仰げば、然して少女は洸惺の思っていた様子ではなく。
「ねね、洸惺くん! これはほんとに虜になっちゃう甘さだよ!」
小瓶いっぱいに蜜を集めてパンケーキにたっぷりかけて食べちゃいたいくらいだなんて。両のてのひらにこんもり乗せたクロリスの花を掲げる命璃の姿に洸惺はつぶらな瞳をぱちぱちと瞬かせた。
「……命璃お姉ちゃんは花より団子みたい」
随分静かにしていたなぁなんて思っていたら、彼女はすっかりクロリスの雫の虜になってしまっていたらしい。
月も星も夜空も。勿論花畑だって全部全部好きだから。このままずっと見ていたいくらいだと続くはずだった言葉は『しょうがないなぁ』なんて笑い声に溶けていった。
「洸惺くんも! はいっ。今はお手手が使えないでしょう?」
「ええっ?」
ついと鼻先に運ばれたあおい花に驚きながらも恐る恐る洸惺もクロリスを口に含めば、それだけで微睡むゆめのなかに誘い込まれたみたいだと黒き天馬は長い尾っぽをゆらゆらと揺らして快を示す。
「うんうん、本当に甘くてすごく美味しいね!」
「ね! 一夜しか咲かないって残念だねぇ」
こんなにも甘くて素敵なのに。勿体無いよねぇ、なんてうっとりと目を細める命璃の言葉に『味わいすぎないように気をつけなくちゃね』なんて返ってくるものだから。よくばりすぎちゃったかな、なんて命璃の頬がほのかに朱を帯びるのには気付かないふりをして。
「このまま果てまで走ってみようか」
どうかな、と呼び掛ける声は変わらずやさしい。それがうれしくて、わくわくして。この先にどんな世界が広がっているんだろうなんて、途方も無いゆめの続きを紡いでしまいそうになる。
「空と海が交わる場所。目指してみちゃう? ふふっ。それなら早速……洸惺くん、レッツゴー!」
ひとの足よりも早く、軽く。風とひとつになってあおいろに飛び込んだふたりのすがたが月に照らされ、ふ、と宙へと躍り出したかのように映った。
本当に月や星に手が届いてしまいそうだ。
地を蹴るたびにクロリスの花が余韻を連れて満ちる空気に甘さを運んでくる。散った花弁が風に遊んで舞い上がってくるのが、まるで花の雨みたいで――、
「……。……あれ、上からも……?」
地面から巻き上がるものとは違う。ぱらぱらと、ちらほらと、洸惺の視界の上から振ってくるあおい花に首を傾げて。けれども走っている最中に振り返ることは出来ないから、もしやと思い当たる節を問うべく声だけで背後に語り掛ける。
「命璃お姉ちゃん、僕の背中でこっそり蜜食べてない?」
「すごいね、ほんとにそらと境目がなくなっちゃったみたい……、……あ、バレちゃった?」
だってだって、あんまり美味しかったから。一年に一度しか食べられないって言われたから。つい、なんて。もごもごと背中で口籠るのがおかしくて、ふふ、と洸惺が微かに笑えば命璃は慌ててぶんぶんとかぶりを振って否を唱えた。
「か、隠し持ってないよ? 持ってないからね!? 命璃ちゃんは嘘つかないもん!」
隠し持ってなんていませんともと、何度も念を押してくるものだから。逆にかくしごとが詳らかにされていってしまっていることに、命璃は気付いているのだろうか。
「うーん、やっぱり怪しいよ?」
すこしだけ悪戯に問い掛けて見せたなら、ほら。
かくしごとが苦手なあなたは、『……嘘だけど』なんてちいさな声ですぐに打ち明けてしまうんだ。
●『| 《ブランク》』
青い、蒼い、碧い。
どの言葉でも言い表せない程のあおいろを、クラウス・イーザリー(希望を忘れた兵士・h05015)は我を忘れてしまったかのように呆然と立ち尽くし見惚れていた。
「すごい……」
沢山の√を渡り歩いた。戦火に燃ゆる大地から斜陽に停滞した暗澹たる世界も。時にはあやかしに化かされかけたこともあったか。でも、それでも、まだ足りない。まだ見ぬ未知が、息を呑むほどの光景が、沢山の平行世界の中に途方も無いくらい広がっているのだと。知らず止めてしまっていた息を吸い込めば臓腑いっぱいに花のあまい香りが満たされて、この現実味のない光景を五感が漸く受け止めることが出来たような気がした。
「(まるで夢でも見ているみたいだ)」
どこか浮遊しているような心地のまま恐る恐るに腰を下ろせば、風に揺れる花々が微かにさやさやと音を立てる。戦うことしか知らなかったクラウスにとってその囁きは常ならば単なる音としか認識出来なかったけれど、『もしかしたら、見知らぬ人間が来たことを噂しているのかもな』なんて、胸の中に降って湧いた言葉は自覚しないまま。鮮やかなあおいろを確と目に焼き付けてからクラウスはそっと花のひとつに手を伸ばす。
「……甘い」
機能性栄養食に求められるものは効率。味は二の次ばかりのそれらに慣れた味覚にはあまりにも鮮烈すぎて、くらくらしそうだ。もし己がこのまま戦場で命を落とさずに生き延びたとして、戦士たちと肩を並べ盃を交わすようになったなら、ああ。酩酊すると云うことは、ひょっとしたらこんな心地なのかもしれない。
今目の前にあるこの光景も、海の奥底に広がっている景色も。死|んだ親《Anker》友と共に見れたなら、どれほど。
「(わだつみのブルー・ムーンは、ひとときだけでも)」
この『うつろ』を埋めてくれるだろうか。
希望は疾うに捨てた。それでも、こんなにも現実味のない世界なら、或いは。
今まで感じたことのない甘さに酔い痴れながらクラウスは微かに笑みに満たぬ吐息を溢す。その姿を、青い花だけが静かに見つめていた。
●いのちのいろ
澄んだ空気のお陰だろうか、星が随分近くに見える。空から落ちていく星の雫と花のあわいが交わって、まるで辺り一面すべてが淡くひかりを帯びているようだった。
「なんて美しい景色なのでしょう……!」
ふわふわの垂れたけものの耳を期待に揺らして、黎明の瞳に星のひかりを映して。ラデュレ・ディア(迷走Fable・h07529)は知らず胸の前で手を組み合わせながらうつくしいあおいろをぐるりと見回す。
青はただ静かでやさしい色だとばかり思っていたけれど、目前に広がるいのちのいろはめらめらと燃える青い炎のような烈しさを少女に感じさせた。たった一夜限りのいのちを燃やして咲き誇る花。こんなにも鮮烈ないろは、御伽噺の中でだって見たことがない。
「いい香り……これがクロリスのお花なのですね」
胸いっぱいに花の香りを満たせばからだの中から甘さが香ってくるかのようだった。誰もが虜になってしまうと云う花の蜜も、水の中を自在に遊泳できると言われる伝承もこの胸を甚く擽って、物語の『そのさき』を知りたいと身体の奥底から好奇心がどんどん溢れてくる。甘いしあわせに満たされながら、ラデュレは多くを傷付けぬように慎重に、ぷつん、と花のひとつを手に取って口に運んだ。
「……! おいしい」
それは熟した桃よりもあまく、どんな紅茶よりも芳しい。時計の針を一生懸命遡ってみてもいままで口にしてきたどれとも違って、それなのにどこか懐かしい。なるほど、このどこか郷愁を誘う味が人々の心を掴んで離さないのかも、なんて。ゆめのような甘さに揺蕩いながら、ラデュレは夢みがちな瞳を柔く撓めて感嘆の吐息を溢す。
見渡した一面のあおいろはどこまでも澄んでいてうつくしい。
このまま時が止まってしまいそうな、時間を忘れて漂ってしまいそうな気さえしてしまうけれど――踏み出した先に広がる世界はきっとまだ見ぬあおいろを教えてくれる。うさぎの迷い子は物語の頁を捲る旅を暫し止め、今はただ、戯れ合う花々の声に耳を傾けた。
●こぼれたかけら
満ち満ちる月と星の煌めきが雨のように絶え間なく降ってくる。瑠璃を融いたかの如き天蓋をそのまま映し出す海に果ては見えず、時折落ちる波紋はまるで大海が呼吸をしているようだった。
「本当に、夢のよう」
視界を埋め尽くさんばかりのうつくしいあおいろが宿す煌めきを真昼の海の双眸に宿して、シルフィカ・フィリアーヌ(夜明けのミルフィオリ・h01194)は望洋と広がる自然が生み出すたった一度きりの色彩に息を呑む。深く息を吸い込めば身体の隅々まであまく優しい香りが満ちていくことに、心がふるえているのを確かに感じていた。
「(……わたしは、)」
ここではないどこかで、いつか。こんな青い世界を見たことがあるような気がする。
根拠はない。証明してくれるひとだって――少なくとも今はまだ、見つけられないままでいる。それでもシルフィカの胸には予感めいた|もしも《いつか》があって、時折脳裏を掠めるたくさんの『もしも』は、正しくシルフィカが歩んできた『いつか』のかけらに他ならないのだろう。
「……不思議ね」
すべてを失くしてひとの身に堕ちたことを後悔はしていない。それなのに、心のどこかでどうしようもなく嘗て歩んできた道を、えにしを取り戻したいと願っている自分がいることも自覚していた。
「(この青色に触れているからかしら)」
常は注意深く意識している訳ではないのに何故か郷愁を誘われてしまうのは。目前に広がるあおいろが、こんなにもうつくしいから? それとも。
「一夜限りの世界を切り取ることを、許してね」
波音に混ざって数度、スマートフォンに内蔵されたカメラのシャッター音が辺りに響く。てのひらの中のパレットにのせられたクロリスのあおいろに目を細め、シルフィカはそっと花のひとつに手を伸ばした。
「水底に眠る月にも、出逢ってみたいの」
この感情を明快に表す答えは今はまだ出ない。それでもきっと、切っ掛けは彼らが与えてくれる。
蜜の甘さに目を瞠った少女を見上げる花々が、風に揺れながらくすくすと咲っている気がした。
●天をなぞる
すべてが噎せ返るかのような真昼のそらは澄み切って、それと同時に目に見えぬひかりの質量で以ってこちらを圧触しながら押し潰してくる。鮮やかに過ぎる真夏の青でこの胸は充分に満ち足りている筈だけれど。
「(はて、何故かの)」
不意に地に咲いたそれを見たいと思ったのは気まぐれか、好奇心か――或いはその両方か。ひとの子に混じって船に揺られるのも悪くはないと、ツェイ・ユン・ルシャーガ(御伽騙・h00224)は青白い焔を浮かべた双眸を柔らかく細めていた。
「ほう、これは……」
船から降りたツェイの爪先は地に着く一歩手前でぴたりと止まり、そのままそこに大地が続いているかのように身体を宙空に留めたまま前へと進ませる。緩やかな歩調はまるで重力を感じさせず、まるで彼そのものが霧か霞で出来ているかのように花を踏まぬ程度の高さを保っていた。
うつくしい青だった。
見たこともない花に違いないのに何処か懐かしい。幸福の中に寂しさが絡まり合って刺戟されていくような、不思議な心地が胸の奥底から水が沁み入るようにじわりじわりと滲んでくる。
「嗚呼……そうだの」
それが不快なものに感じられなかったのは、そうだ。今は遠く記憶の彼方に仕舞い込まれていたもの。里に咲いていたあの花と同じいろ。嘗て母が愛し、父が護ったもののひとつ――。
「(……我では永らえてやれなんだが)」
面影は里と共にとうに枯れ果て失われた。もう随分忘れて久しかった懐かしい輪郭をなぞれば、舞い上がる甘い香りも微かに苦さを帯びるよう。
「すこしばかり分けて貰うことを許しておくれ」
屈んだ先の花影にゆびさきを伸ばせば、茎を覆う産毛が触れてほんの少しだけこそばゆい。口に含めば思い出ごと包み込むようなまろい甘さがいっぱいに広がって、ツェイは緩やかに睫毛を伏せて微笑んだ。
後は暫し。紡がれたひかりの糸が導く今宵の白道のおわりまで、伸びゆくあおいろの中、月の旅路を見守ろう。
ひとならざるものの揺らめく煙り角が、明滅する星のひかりを受けてきらきらと輝いていた。
●ゆめ、うつつ
「ふわあ……! すごい、すごい……!」
あまく澄んだ声音は弾み、然れどもうたになりはしない。継歌・うつろ(継ぎ接ぎの言の葉・h07609)の爪先が踊るたび、クロリスたちは応えるようにあまい香りを立ち昇らせる。
「花は好きだが、くろりすなる花の名は初めて聞いた。さすが異世界だな」
クロリス、ニゲラ。あおいろの花の名前。
うつろの知らない言葉たち。継ぎ接ぎの引き出しのなかにはない、うつくしくまぶしいもの。綿が水を吸い上げるように学び続ける少女の様子を、傍らで同じくして歩を進めていた神花・天藍(徒恋・h07001)は常よりも幾分やわらかな視線で以って追い掛けていた。
「あっ……!? てっ、天藍さん、ごめんなさい」
「……うん?」
不意に花が戯れ合うようにくるくるとスカートの裾を翻していたうつろの足がぴたりと止まり、次には謝罪の言葉を口にするものだから。忘れたとは何のことだろうかと次ぐ音を紡ごうとするけれど、答えはすぐに少女が教えてくれた。
「ごあいさつ、わすれちゃった」
礼節を欠かさぬ少女の在り様を無碍にするほど捻てはおらぬと、天藍は軽く片手を上げて違えた彩を宿す双眸を僅かに細めそれを制した。
「畏まった場でもないのだ、楽にするとよい」
この場は神々の座に非ず、であれば肩肘を張る必要もない。無垢なる冬の化身がそう告げるのにきょとんと目を丸くしたうつろはそれでもと深々と頭を下げるのだった。
「今日は、よろしく、おねがいします」
「律儀な奴だ。ま、それもお前の美徳か」
蒼の空、蒼の花。
世界線をほんの少し違えただけでこれほどまでに生きるものたちは姿かたちを変えるのか。いや、それでも。
「星月が変わらず美しいのは良いことだ」
「お星さま、お月さま、それに、たっくさんの青い花……これが、クロリス」
きれいだね、と不器用に笑ううつろが花の前で屈むのに倣って天藍もそっと膝を折る。近付けば花々の囁き声さえ聞こえてきそうで、『どんなおはなしをしてるのかなあ』と首を傾げる少女に天藍も『そうさな』と短くいらえた。
「ほんとうに、これに、あまーいみつがあるの?」
「ふむ。星詠みが言っていた甘美なる花の蜜か……どれ」
こう見えて甘いものは嫌いではない。年に一度きりの甘露となれば興味もそそられようものだと、ひとつだけ手折った花を躊躇いなく口にする先達をそわそわと見つめていたなら、ふ、と微かに吐息を溢して微笑むものだから。びくりと微かに肩を揺らしたうつろは恐る恐る口を開く。
「えっ、天藍さん……!? ……おいしい? 苦く、ない?」
それを苦笑と取ったのだろうか、不安げに瞳を揺らす少女に喉奥で笑いを殺しながら口元を袖で隠し『お前も吸ってみろ』と促せば、おっかなびっくり、恐々と手を伸ばしたうつろもぎゅっと意を決するように目を瞑ってからクロリスの花を唇へ運ぶ。
「……〜〜!」
ひとつの花から吸える蜜の量はふたしずくくらいのはずなのに。じゅわ、と口の中で甘さがいっぱいに弾けたみたいで、熟し切った果実に歯を立てたみたいだ。今まで味わったなによりも甘美な蜜の味に言葉を失ってしまえば、その様子を見ていた天藍も美味いだろうと言葉を重ね頷きを返した。
「(うつろは災厄としてはあまりにも優しい)」
どうかこのまま歪まずに。うつくしいものだけを彼女が見て行けるようにと願いながら。ぱちぱちと瞳の奥で星を煌めかせる少女の姿に天藍は僅かに視線を伏せて想いを馳せる。
「あ、そういえば……『とりこ』って、どういう意味なのかな……?」
「虜というのは夢中になると言うことだ」
いつか、どこか。遠くない未来に、その胸を掴んで離さぬ存在に出逢えたなら。お前に意味を与えてくれる存在が現れてくれればよいと願わずにはいられない。
「それじゃあ、今は。わたし、このお花のとりこ、だね」
|さいやく《さいわい》が無邪気に綻ぶ。
その横顔を、冬の輪郭はただ優しく見守っていた。
●きまぐれ、きみと
「ま、また説明なく掻っ攫われた……!」
潮風に髪を遊ばせながら戀ヶ仲・くるり(Rolling days・h01025)は『これどこ行ってるんですか』と最早幾度繰り返したか分からぬ問いを傍らに立つ雨夜・氷月(壊月・h00493)へと向ける。けれど意味深に微笑む彼は『良いとこだよ』としか答えてくれず、その奔放さはつい最近まで平凡な女子高生であった筈のくるりに御しきれるものでは到底ありはしなかった。
「着いたよ」
拉致とは人聞きの悪い、遊びに連れてきただけ。本人の合意を取っていないだけで悪意はこれっぽっちもありはしないのだと。振り返った氷月が微笑みながらタラップへと促せば、『合意がなかったら拉致なんですよ』ともごもご口籠る少女は漸く彼が連れて来たかったと言う世界の全容を視界に収め、その光景に大きく息を呑んだ。
「わ、すご、きれい……視界いっぱい、青い花……!」
島じゅうをいっぱいに埋め尽くした青い――名前はなんと言うのだろう――うつくしい花々の姿。まるで現実味のない景色に朝靄の瞳をまんまるにしながら、くるりは夢でも見ているかのような心地でほう、と感嘆の息を溢す。
「この前の薔薇のお茶会といい、氷月さん、お花好きなんですか?」
このあおいろとは対照的な大輪の薔薇の庭。あの場所だってとても素敵だったけれど、それが彼の趣味なのだと思えば納得出来ようものだった。いや、それにしたって何処に何をしに行くかくらいは事前に伝えてもらいたいが。
「うん? 特にそういうワケじゃないけど。くるりと遊びに来た先が偶々だね」
こういうトコに誰かと行くならオンナノコとじゃない? なんて。さらりとそういう事を平然と言ってのける辺りがオトナなんだなぁと感心する部分もあろうものだが、いや、いやいや。
「……オンナノコ扱いしてくれるなら、先に説明してくださいよ……」
唸り始める少女の様子などどこ吹く風、ひょいと身を屈めた氷月の長いゆびさきが青い花をぷつんと摘めばそのまま難しい顔をしたままのくるりの眼前につい、と突き出した。
「はい、くるり。この花の蜜吸って」
「蜜? この花の? 吸う?」
それって大丈夫なんですか、とか。口に出さずとも顔に出ているくるりにはお構いなしに手本を見せるように花に唇を寄せたなら、退路を断たれた哀れな少女も恐る恐るに青い花を食む。
「え、うわ、……甘ぁい……」
「あ、ホントだ。話に聞いてたけどあっまいねぇ」
口にし慣れたチョコレートやキャンディとは異なる。かと言ってこれらに近しい果物も記憶の中には見当たらない。口いっぱいに広がる芳醇な香りはすぐに溶けて、さらりと喉奥へと消えていく。今まで食べたことのない味は、花の香りがそう感じさせているのだろうか。
「えー、おいしい……もうひとつ摘んじゃおうかなぁ」
「この蜜口に含んだら海の中を自由に歩けるって不思議。あ、この後だけど海の底に行くからね」
彼は一体何を言っているのだろう。このうつくしいあおいろの中にダイビングスーツのレンタルなんてある訳ないし、いや、蜜を飲んだら海の中を歩けるって何?
「海の底に行く?? 聞いてませんけど??」
「んっふふ、今言った」
「だから先に言ってくださいよぉ!?」
内緒にしていたほうが面白いからと。悪びれなく告げる氷月は可笑げに目を細めながら『それにね』と口を開く。
「海の底では月がみたかったもの、あいたかったひとに会わせてくれるんだって。なにか願い事があるなら考えておくといいよ」
――あいたいひと。
氷月が紡いだその言葉に、くるりの双眸がぎゅっときつく細まる。会いたい人がいない筈なんてない。それこそが自身の欠落に他ならず、何度も諦めようとしたのだから。
「……分かってて連れてきました?」
「……ははっ、どうだろうね?」
眉を寄せて睨まれたって、ちっとも怖くなんかありはしないのに。
『ありがとうは、言いませんから』と呟くくるりに、氷月は雨垂れの瞳を三日月に撓めいっそう甘ったるく微笑んだ。
●地に、空に
「孤島に咲く青い花、ねェ」
「主は好きだろう?」
孤島に咲く一夜限りの花。青い景色も、それを成す花の姿も。主にとっては好ましいと感じるものであろうと、同意を求めるトゥルエノ・トニトルス (coup de foudre・h06535)の瞳が泡を弾いたように煌めくのは、同じくらいに広がるあおいろが澄んでいるからだろうか。まるで幼い子どもに戻ったかのように燥ぐその姿に、緇・カナト(hellhound・h02325)は微かに吐息を溢して微笑む。
「斯様なウワサを耳にして赴かぬ訳にはいくまい!」
「はいはい、お前のお呼びとあらば」
着いていけば良いんだろうなんて。少し捻くれた返事とてそれが彼の肯定であることを知っている。それ故にこくこくと何度も頷くトゥルエノに毒気を抜かれたのか、カナトは軽く肩を竦めた。『こういった風情のもの』を見付けてくるのが得意な片割れが見せてくれる景色はどこまでも澄んでいて、それを真っ直ぐ受け止めるには躊躇ってしまうことも多いけれど。
「それでは一面に広がる、あおいろを目指していざ行かん!」
こんなにも嬉しそうな姿を見せてくれるのだから、ここまで船に揺られてきた甲斐はあったな、なんて。黒妖の写身はやわらかく鈍色の双眸を細め一夜限りの青の天蓋へと足を踏み出した。
月が、星が、煌々と降り注ぐ。
真昼のそらとも違う。かといって暗澹たる闇の中とも違う。己の知る『青』とは異なる、けれどそれが『あおいろ』だと確りと認識出来る。絵画を現実に運び込んだら、こんな景色なのだろうか。
「空とも海とも異なる青色の上を歩くというのも、不思議なものだな」
「へぇ……雷の精霊にもそんな感覚あるんだな」
トゥルエノはひとならざるものだ。無論カナトも大まかな括りで言えばそうなのだが、彼はもっとずっと自然界に溶け込む概念に分類されるもの。定命のものとは異なる観念を持つ精霊たる少年がそのような『人間くさい』ことを口にすることが何だかおかしくて。それをそのまま口にすれば、気分を害した風もなくトゥルエノはころころと可笑げに笑った。
「人間ではない……精霊であっても、そういう気持ちを感ずることもあるさ」
「ふうん。……お前とこういう場所を歩くのは如何なんだろうな」
未知への関心は絶えぬ。それがお前と共にあるならば尚のことだと続けるも、カナトがぽつりと溢した言葉にそのうつくしい天雷の瞳を僅かに伏せて少年は一度口を噤んだ。
「我とこういった景色を歩むのは好まないか?」
ひとの描く|さいはて《てんごく》は、丁度こんな風に一面に花が咲き乱れた理想郷なのだと云う。暗い森。青い花。雨が去る気配と、月明かり。あの日見た景色にも似て、ああ、だからこそ少しだけ――。
「青い夜空に、青い花畑……別に嫌いな訳ではないんだ」
「……ならば別に良いのだ!」
殊更に明るい声を上げたトゥルエノに、俯き掛けたカナトが数度瞬く。
「夢のような花畑でも、訪れることなきような海底でも。幾らでも共に向かうとしようじゃないか」
無邪気で奔放で、揶揄うようで、それでいて真っ直ぐで。きっと、この先に待つ海のさいはてまで訪れることも、『その先』も彼には見えているのだろう。
夢を見るなんて柄でもない。それでも、このひかりを追い掛けるのは、悪くない。
「お前がイイなら、其れで良いんだろう。屹度」
「うむ! ……おお、そういえば花の蜜が必要という話だったか? 主も食せ!」
手折る花はひとつずつ。馬鹿みたいに甘ったるくて、それなのに何故だろうか、酷く懐かしい。痛みを堪えるように目を眇めるカナトを見上げ、幼き雷獣は『美味だ』と笑った。
「こういうものを味わうのも、また経験というのだろうなぁ」
そらに、海に。広がる月に、何を願おう。
踊る胸の鼓動のままに口元を綻ばせるトゥルエノの横顔を、星々のひかりがやわらかく照らしていた。
●咲いて、咲って
あぶくが弾けたみたいに散る星の海の中に、ぽっかりとしろい月が浮かんでいる。
寄り添いながら、花々が戯れ合うように。風に、青に互いがさらわれないようにと、ララ・キルシュネーテ(白虹迦楼羅・h00189)はセレネ・デルフィ(泡沫の空・h03434)のしろく細い手を取り愛らしい唇をそっと開いた。
「あの月は青の穹に抱かれたお前のようよ、セレネ」
息を呑む声が間近で聞こえる。彼女が咄嗟に上げ掛けた否定の言葉を飲み込んでくれたことが分かるから、ララは繋いだ手をゆらりと揺らして彼女が懸命に紡いでくれようとしてくれている優しい言葉を待った。
「……そう言われると照れてしまいます、ね」
月と星と。広がるあおいろのせかいはとても美しく、まるであなたの翼のような夜だ、なんて。自慢の翼を誉めてくれたことに星空を写した羽を揺らして笑みを咲かせれば、戸惑うように瞳を揺らしていたセレネも薄く頬を染めながら微笑んでくれた。
「一年に一度だけ……だからこんなに美しいのかしら」
「そんな貴重な景色。ララさんと一緒に見られて嬉しい」
ほら、セレネはララが欲しい言葉をいちばんにくれる。
綻ぶようにはにかむセレネの姿が嬉しくて、ララはますますに笑みを深めてくるりと服の裾を花弁のように踊らせた。
「セレネと一緒だからよりいっそうに、よ」
いのちの全てに竜漿を宿すこの世界は神秘に満ちている。神とて例外ではないのだと云うのは目を瞠るばかりだが、そのお陰で漏れなく祝福を身に受けることが叶うことはさいわいであった。
「ララ、まだ泳げないけど……セレネは泳げる?」
時にずっと大人びて見えるララがそんな可愛らしいことを口にするものだから、知らず緩みそうになる口元にてのひらを添えてセレネはそっと頷きを返す。
「私は泳ぐのは……少しだけ。でも、大丈夫ですよ」
クロリスの花を口にしたなら、青の扉を潜ることが叶う。
摘み取ってしまうことは少し勿体無い気もするけれど、試してみないかと首を傾けたなら、むくれたようなララの柔い頬が今度はぱっと喜色に染まって、今度こそセレネはくすりと小さく笑った。
「ララさんが溺れないように。ね?」
「試してみるわ。セレネも一緒よ」
甘い香りも花蜜も、全て美味しく頂くの。そう意気込むララが手にした青い花は然してその口元には運ばれず、うんと背伸びしたちいさな手がセレネの顔の近くまで伸びてきたものだから、ぱちりと瞳を瞬かせてセレネはそっと身を屈めてララを覗き込む。
「セレネ、ほら。あーんして。ララが花蜜を飲ませてあげる」
「え、えっと……あーん」
気恥ずかしさが湧いてくるけれど、無邪気な彼女の申し出を無碍に出来る筈もない。恐る恐るに口を寄せれば運ばれたクロリスの蜜が口いっぱいに広がって、ゆめに誘われてしまいそうなほどの甘さにあおい瞳が緩やかに瞬いた。
「どう? 美味しい?」
「……! あまい……おいしいです」
ララさんも、と促す声にぱくりと萼を食んだなら寝物語の中に広がる夢のような心地が胸の中に満ちていくようで。『美味しい』と視線を交わし合えばゆめの続きを共有できているような心地になって、くすりと少女たちは咲い合う。
「……ね、ララさん。ララさんはねがいごとはありますか?」
内緒話のように囁き合えば、花の囀りがきっと隠してくれる。こそりとセレネが問い掛けるのに、ララは甘やかに瞳を細めてそれにいらえた。
「そうね。ララの願い事は」
――大好きな人達がずっと、ララの傍で咲っていてほしいわ。
子どもらしい純粋さで。神が如き強欲さで以て零されたねがいは、彼女の純真さからくる真実なのだろう。それを眩く思いながら、セレネもそっと己の胸に抱くねがいの輪郭を口にする。
「私は……みなさんの幸せな姿をちかくでみていられたら、と」
いつか崩れてしまうかもしれないけれど。せめて、わたしが消えてしまう前に。
少女たちの願いを抱いて、月は静かに海へと続く道を照らし出していた。
●満ち満ちるさいわいよ
「すごい! ブルークロリスイースターだー!!」
臓腑に澄んだ空気を満たせば気分も晴れ渡るかのようだと。沁み入るように感慨に耽っていた咲樂・祝光(曙光・h07945)の心地良い静寂を賑やかに打ち破りながら青い花々と戯れるようにひらりと舞う薄紅。くるりくるりと踊るように跳び回っては忙しく跳ねる長耳に肩を落としながら祝光は春の化身へと声を張る。
「エオストレ!」
神秘が紡いだ一夜の奇跡。それってば最早|桜禍祝祭《イースター》に違いなくって――夏? そんなの関係ないない! とは、エオストレ・イースター(桜のソワレ・h00475)の意。溜息を吐く祝光とは対照的にエオストレは桜宵の双眸に星々を浮かべながら華やぐ歓声を上げていた。
「折角の青の世界をイースターにするなよ?」
自分も桜は好きだけれど、ここはクロリスの花畑だからいいのだと。今一度念を押せばエオストレは拗ねたように唇を尖らせながらも、口うるさく世話を焼いてくれる幼馴染のお小言を何処か浮き立った気持ちで受け止めていた。
「わかってるよーブルークロリスイースターは青いからいいんだ」
今日は桜はお預けでーす、なんて。ご機嫌にうたうエオストレに置いていかれないように足を運びながら、祝光は改めてぐるりとあおいろの絨毯を見回せば、ふと。気まぐれに足を止めた長耳の少年が長いコンパスを軸にして振り返る。
「君は月に何を願うの?」
無垢な問いに宵と暁月のあわいに揺れる瞳を眇めて龍の蕾はほんの少しの逡巡を挟む。それは言葉を選んでいるようにも、口にすることを躊躇っているかのようにも見えた。
「……願わくば」
――妹達や家族に逢いたいものだ。
それはエオストレにとってある種予想できた答えであった。彼の妹の居場所ならば知っている。けれど、それを自分が口にするべきなのか――答えは未だ出ないから、その全てを口にすることは出来なかった。
「……ん、僕は世界中がハッピーイースターになってほしい!」
だから、エオストレはただ咲う。
まじないのように口にするその言葉だって、自分の本心に他ならないから。
まじと膝を突き合わせて屈み込んだ視線の先。それぞれ手にしたクロリスの花を見つめながら、先に滴る雫を口にしたのは祝光の方であった。彼がその瞳をまんまるに見開くのを目にしたエオストレもまた、えいやと花を口に運んだなら。熟し切った果実が口の中で弾けたような甘みが口いっぱいに広がって、あまりの甘美な衝撃に思わずぴょんと跳ねてしまう。
「「……美味しい!」」
このあまいあまい花蜜が齎すさいわいが、味覚だけでなく水の中を自在に歩めるようにしてくれるだなんて。そうでなくても泳げるから問題はないと祝光が頷けば、虚を突かれたような声を上げた少年の長耳が力なく垂れていく。
「ぼ、僕はスイミングイースターになれば……問題ない……はず」
「……その返答には不安が残るな」
クロリスに夢中で海に入ることまで考えていなかったのであろうエオストレが視線を泳がす様子にちいさく吹き出せば、それを咎めるように軽くぽかりと肩を叩かれて、おかしくなってまた笑ってしまった。
「……ん?」
不意に、花が不自然にかさかさと揺れるから。ふたり揃って視線を下に落とせば、一体いつからそうしていたのか。ふくふくの茶色い縞模様を浮かべた猫又のミコトが夢中でクロリスの花に顔を突っ込んでいるのを見とめて慌てて祝光は屈んで手を伸ばす。
「君の猫、大丈夫なの? 爆なめじゃん」
「こら! ミコト! 舐めすぎだろう!?」
まるで油を舐める猫又だ。いや、正しく猫又ではあるのだが。取り憑かれたように花の蜜を求めるミコトの執念は凄まじく、祝光が引き剥がそうとしても直ぐにぬるりと手からすり抜けてしまう。
「エオストレ、見てないで手伝ってくれ!」
「え!? 無理だよしがみついてるし!」
結局。食いしん坊の猫又のおなかが月のようにぽこんと丸くなるまで、ふたりの少年はその場を動けなくなってしまったのだとは、月と星々だけが知る話である。
●机上には留まらぬ
「ふむ。伝承の通りだな、壮観の一言に尽きる」
どうだ、夜に見る『蒼』も中々のものだろうと。にんまりとねこの様に目を細めるウィルフェベナ・アストリッド(奇才の錬金術師・h04809)は、まるでこの光景を予知してきたかのような口ぶりで。稀代の錬金術師と名高い彼女の叡智を以てすれば、成る程クロリスの伝承を知っていてもおかしく――、
「何となくそうかなとは思ってたけど、やっぱり師匠知ってたんかい?!」
千堂・奏眞(千変万化の錬金銃士・h00700)が声を張り上げる様にからからと笑う彼女は無邪気なものだけれど、本当にこの竜の血を継ぐ者達の大地の殆どを見聞き、或いは踏破しているのかもしれない。
「……ていうか、何でそこで『蒼』を強調しながらオレを見てくんの、師匠……」
「さてな?」
この身に宿すは蒼穹の。けれどその全てを口にはしない。
やれやれと肩を竦める奏眞を尻目に、ウィルフェベナはさっさとクロリスの持つ神秘の検証へと移ろうとしていた。その背を追い掛けようとした矢先に師弟のもとへ真っ直ぐに駆け寄ってくる少女の姿が視界に留まり、それが霧谷・レイ(自称 「神秘の美少女錬金騎士」・h03818)であると知れば奏眞はこっちだと軽く手を振ってそれに応えた。
「すみません、お待たせしましたっ!」
「おお。バカ弟子の仲間の一人に逢えて何よりだ」
『奏眞の友人に出逢えたことを嬉しく思う』。正しくはそのような含みを持つ言葉である筈。少しばかり尊大な物言いに面食らってしまうけれど、師匠はいつもこうなんだと申し訳なさそうに奏眞がてのひらを合わせる姿がなんだかおかしくて、レイはなるほどと頷きを返して改めてぺこりと頭を下げた。
「は、初めまして、ウィルフェベナさん! 霧谷レイ、√ウォーゾーンの戦士で錬金術師です! 一応専攻は金属の形態操作!」
「うむ。私はウィルフェベナ・アストリッド――まぁ、それなりに名の売れた薬学を専攻している錬金術師だ」
以後よろしく頼むぞ、と。初対面同士が互いに名乗り合うことに奏眞が胸を撫で下ろしたのも束の間のこと。『ところで』と師が次ぐ言葉を紡ぐのに、少女はことりと首を傾ぎ、少年はぎくりと肩を揺らして息を呑んだ。
花はその多種多様性から、錬金術に於いて様々な触媒として扱われる。
魔法が当たり前のように存在する√ドラゴンファンタジーであればそれは一層顕著であり、より神秘性の高い逸話を持つクロリスの花のようなものであれば尚更付加価値は高まるのだと、教鞭を手繰るようについと指先を宙に滑らせたウィルフェベナは若き錬金術師たちを降り仰ぐ。
「さて、錬金術師としてお前らに聞こう。この花の蜜が齎す、すべてのアオが混ざった世界に興味はあるか?」
彼女は問うているのだ。クロリスのちからで潜った青い扉の先に広がる光景に、『錬金術師として興味はあるか』と。
「(……ものすんげーズルい言い方をしてきてるし)」
天才、奇才と呼ばれる者たちはどうしてこうも回りくどいのか。
師匠はその言葉を要約すれば『海に潜ろう』と自分たちに言っているに違いない。素直に言ってくれれば可愛げもあろうものだけれど。彼女の名誉のために奏眞はその全てを口にはしないが、はあ、とちいさく息を吐き出しながら師と改めて向き直る。
「まぁ、義体部分は|水の精霊《レニー》に保護してもらうから、大丈夫だけども……」
「えっと、海に潜るなんて、もちろんとっても楽しみです? ……ってことであってます?」
レイの視線は僅かに泳ぎ、次第に傍らの奏眞へと通訳を求めるように流れていく。そそくさと友人のもとへ歩み寄れば、恐る恐る『あってる?』ともう一度問うてくるものだから、困ったように笑った奏眞はなんかゴメン、と言葉を重ねながら間違ってはいないと深く頷いた。
「千堂くんの師匠ってどんな方かと思ったら、あたしでも知ってる有名人じゃん!」
変わり者だって聞いたことがあるけど、大丈夫? なんて。気遣いを多分に含んだ友の言葉に、気苦労の絶えない奏眞は心の涙を溢しながら『大丈夫』と肩を落とす。
「いつも我が道を行く過程で……周りを振り回すだけ……ではあるんだよ、うん……」
それは本当に大丈夫なのだろうか。
若者達の不安を尻目に、ふたりの承諾を得られたウィルフェベナは上機嫌に笑みを深めるのであった。
●なみだのわけ
真昼のうちはすすべてが眩しくて、強すぎるひかりに焼かれてしまいそうなほど。だからせめて、視界だけでも涼やかに――そう思って船旅へ同行を決めたナギ・オルファンジア(■からの堕慧仔・h05496)は目前に広がる光景にちいさな感嘆を溢して周囲を見回した。
「これはこれは、見事なものですねぇ……」
近くにこんなにも広い水場があるからだろうか、肌を撫でる風は熱をさらい、共に揺れる花々の囁き声も涼やかで心地良い。
「本当はクロリス柄の日傘が良かったのだけれど」
薔薇なのはすこしのご愛嬌。可憐な白薔薇をあしらった日傘をてのひらで弄べば薄いレース地を透かすように星明かりが落ちて、ナギのしろい頬を微かに照らした。おろしたてのワンピースの裾がひらりと翻るたび、あまい香りまでもが立ち上って五感の全てに優しく触れてくる。
「(夢見る薫り、というやつかなぁ)」
あまく、やわらかく。深く息を吸い込めば体の隅々までこの青い花に満たされていく。そうと一輪だけ手折った花を口に含めば、忘れた■■もほんの少しばかり満たされていくようだ。
「……ン、蜜もとても甘い」
ひとが禁忌に触れるような魔性ではなく、それこそ伝承のとおり女神が溢した|甘露《涙》と呼ぶに相応しい。唇を僅かに濡らした蜜をぺろりと舌先で拭い、ナギはあまく目を細めた。
――女神が溢した涙、とは。
話の流れを汲み取るに、誰かを想ってのことなのだろうか。
「ナギには未だわからぬ感情ですね」
狂おしいほどの恋は知らぬ。全てを赦す愛も、知らぬ。
それでもこんなにもうつくしい花を咲かすほどの想いであるならば、恋なるものも、愛なるものも。そう悪いものではないのかもしれない。
「ふふ」
おんなは咲う。風に揺れて囁き合う花々が懸命にいのちを燃やす姿の、なんと愛らしい事だろう。
「君たちは今何を想っておいでかしら」
月に焦がれ、星にさざめき、青の祝福を齎す花々よ。
くるりと日傘を手繰るましろの姿も、あおく、あおく。花の香に紛れて染まっていくようだった。
●旅の途
あたらしい靴をおろす瞬間はいつだって胸が踊る。それが自分の歩んできた路で生まれたえにしから紡がれたものであるならばなおのこと。祭那・ラムネ(アフター・ザ・レイン・h06527)はその軽やかさに驚きながらも、ああ、彼らとはじめて歩む道ならばこの幻想的な世界がやはり相応しいものだったと目を細めてはにかんだ。
「な、カエルムさん。見える?」
肌身離さず大切に首に下げたペンダントを軽く掲げたなら、星あかりを受けたあおい輝石が呼び掛けに応じるかのようにきらりと一度大きく煌めく。それが今はもの言えぬ彼の言葉なき返事のような気がして、ラムネはやわく微笑み「よかった」とちいさく、彼にだけ聞こえるように安堵を溢す。
このちいさな竜のかけらと共に旅をしてきた中。ほんとうについ最近のことではあるが、ラムネは同じ空の下で大海原へと足を踏み出した事を思い出していた。
――海が好きだ。
幼い弟妹に読み聞かせた本の中に出てくるそれらは途方もなくひろく、あおく――それでいて、自由だったから。
沈みゆく白い泡が消えゆく様も、永遠まで続くかのようなあおいろも、本当に綺麗だった。旅路を重ねるたび、ひとを知るたび、せかいを知るたび、宝物みたいな思い出が増えていく。
「……この√、本当に物語のなかの世界みたいですごく好きだ」
あの日弟妹とともに夢見た空想が、現実にも存在するのだと知れることが何より嬉しい。
「カエルムさんの冒険譚もいつか聞いてみたいな」
誰より自由を愛した彼がその生涯のうちに見てきた世界は、きっと自分が両手で抱え切れる思い出よりもずっとずっと広いのだろう。名のある竜であったのだから、この世界の何処かに彼を語り継いだ伝承もあるのかもしれないな、なんて。『もしも』を広げれば先の楽しみがいくつも増えていくようで、そんな風に考えられる自分の心の変化も嬉しくて、ラムネは気恥ずかしげに笑みを溢した。
伝承に伝わるブルー・ムーン。一年にたった一度きりしか見ることの出来ないその光景を、彼と共に見たいと思った。
クロリスの花蜜をそうと口にすれば、一瞬でゆめのなかへと攫われてしまいそうなほどのあまさが広がって思わず目を瞠る。なるほど、確かに虜になってしまうひとが絶えないのも理解できるかもしれない。目に見える変化は見られないが、何処か。ほんの少しだけ呼吸がしやすくなったような気がして、ラムネは改めて深く息を吸い込み青い花々の香りを胸いっぱいに満たして目を伏せる。
このあおいろに願うのは。弟妹たち、友人、心の拠り所たる親友の。そして旅の祝福を授けてくれたコルヌの民の、長い、永い幸せを。
「……元気にしてるかなあ、コルヌのみんな」
旅を愛する彼らもまた、同じそらの下のどこかで星を見上げているのだろうか。あのやさしく、あたたかい竜たちに再び巡り会えたなら。旅の話を交わし合えたらいいと――巡りゆくいつかに思いを馳せながら、ラムネは暫し竜のかけらと共に、天と地で混じり合うあおいろを目に焼き付けるように佇んでいた。
●かみさまのおとしもの
もうもうとけぶる水蒸気に大地は覆われ、身体中の水分ごと持っていかれてしまいそうなほどの息苦しい日が続く。真昼のうちはすすべてが眩しくて、強すぎる陽のひかりが地を焦がしてしまうような気さえする。太陽が宵の揺籠の腕にとっぷりと抱かれた今、辺りは心地良い風に包まれて茹だるような暑さを暫し忘れさせてくれた。
「これがクロリスか。確かにニゲラに似ているね」
眼前に広がる一面のあおいろに、ほぅ、と感嘆の息を溢しながら藤春・雪羽(藤紡華雫・h01263)はあまく熟れた果実が如き双眸を細めて咲き誇る花々の香りを胸に満たす。
「ああ……これは美しい」
それに馨も。
微睡むゆめの中に嗅覚を連れてくることが叶うならばこんな馨がするのかもしれない。ああ、でも。それなら目が覚めることが惜しくなってしまうかもしれないな、なんて。余す所なく咲き誇るクロリスのそばに屈み込みながら雪羽は微かに笑みを溢した。
「そういえば、花蜜は甘いと聞いたが……」
一度味わえば虜になってしまうと言われるその蜜は甘味好きにはたまらない情報に違いない。そわそわと尾っぽの先を揺らせば、擽られた花たちが咲うように雪羽の背後でさやさやと忙しく揺れる。
「すまないね。私にも一輪、分けておくれ」
ぷつんと摘み取れば雫が垂れてくるようで、慌てて食めばじゅわりと口いっぱいに幸福が広がってくる。その甘さに思わずきゅっと目を瞑れば、身体の隅々まで甘露に満たされていくかのようだった。
「……ふふ、なんと蠱惑的な味だろう」
女神の涙の名を冠する蜜が齎す祝福。年にたった一夜だけ咲むこの花で華雫を作ったら、一体どんな効能が得られるだろうか――そんないち薬師としての好奇心を擽られつつ。一晩で枯れてしまわなければ研究出来ようものだけど、と。ほんのひとときだけ齎される奇跡に雪羽は幾つも浮かんだ|調合の相性《レシピ》を巡らせながら微かに吐息だけで笑う。
五感全てで堪能できるうつくしい花。
この興味深い縁との出逢いに感謝しようと、うつくしき白靇はどこまでも心地の良い香りにそっと身を委ねた。
●暗愁に消ゆ
この花々がもし太陽を知れたなら、どれほど。
たった一夜の|花《ゆめ》ならば、夢現に微睡んでしまえやしないかと期待する。
「……此処も海みたいだ」
一面に広がる青い花は遠く何処までも広がる海の延長線のよう。
よく知る沈丁花とも金木犀とも違う。鼻腔に広がる馴染みない甘い香りに酔ってしまいそうだった。壊さぬように。潰さぬように。そんな風になにかに触れることはいのちを手折ることよりもずっと難しい。夜鷹・芥(stray・h00864)は満ちる月の如き双眸を伏せ、浮かんだ面影を振り払うよう緩やかにかぶりを振った。
「(逢いたい、か)」
それは呪い。自らが壊し、殺したもの。
疾うにかたちを変えて自らを苛む想いの欠片ごと飲み下すよう、甘やかな蜜を咀嚼する。外した面の下で口吻した花が、月のやわらかなひかりを受けて仄かに輝いたような気がした。
――此の蜜がいっそ猛毒ならば良かった。
そうすればずっと、みなそこの奥深くまで沈んでしまえる。
眸を臥せば奪ってきたいのちが地獄から己を絡め取ろうと手ぐすねを引いて待っている姿が浮かぶ。生きる為に必要な殺しも、不必要な殺しも。コンビニの脂っこい弁当の味も。陽の光の眩しさも、何もかも。その全てが無駄では無かったのだとしても、呪いは今も芥の首を静かに、確かに締め上げて来る。もし、その全てを忘れさせてくれたなら――もう一度、深く眠ることが出来るのかもしれない。
「俺を連れて行ってくれ、クロリス」
瞬きほどの太陽だった。
それなのに、一度ひかりを知ってしまったこの目は焦がれて灼けてしまった。失ったひかりを追い求めることは二度と叶わぬと知りながら、それでもまだ芥は生きている。生かされてしまった。
「ああ……甘いな、酔いそうだ」
青い花の只中で、見上げた星々だけがきっと己の願いを知っているのだろう。
素顔を青に晒したまま。今だけは暗殺者でも警視|庁異能捜《カミガリ》査官でもない――ただの『俺』で在れるようにと。芥はその身をあおいろに沈め、しじまの中へと身を委ねた。
第2章 冒険 『蒼の領域』
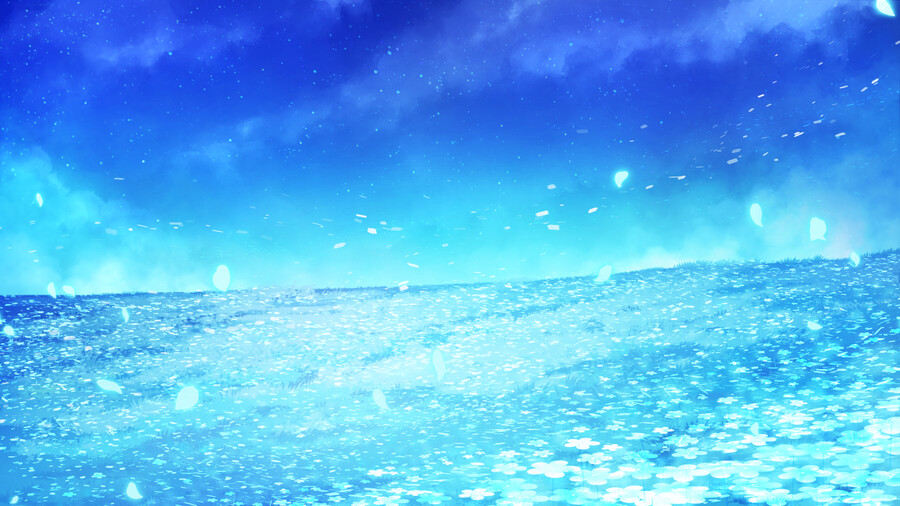
●きみのいのり
そろりと足を水に浸せば、ひやりとした温度だけが肌に伝わって来るようだった。
よくよく目を凝らせば海に身体を預けているはずなのに、からだの表面には薄い空気の膜が張っていて服を濡らしてしまうこともない。それこそまるで本当にクロリスの花畑の延長線であるかのように能力者たちは水の中で呼吸をすることも、声を発することも叶うよう。瞼に水の衝動が少なくなるころに瞬けば、そこには白い砂に溶けていくように滑らかなあおいろがただ静かに広がっていた。
降る星々のひかりを受けてきらびやかに躍動する海の中。月の光だけが真っ直ぐに、深く、深く。本来ならばひかりが届かない遠く果てまで、まるでしるべのように白んだ道を作り出している。このひかりの帯を辿っていけば、きっとその先でみなそこに眠るブルー・ムーンに出逢えるのだろう。
ねがいを、いのりを。その胸に宿して――今はただ、このあおいろに揺られていよう。
道は天の月が示してくれる。
どうかこわがらないで。海はすべてのいのちを、優しく抱いてくれるから。
- - - - - - - - - -
第二章の舞台では月のひかりを辿りながら海底を目指して進んでいきます。
昼間よりすこし大人しい色とりどりの小魚たちと触れ合ってみたり、みなそこで待つブルー・ムーンやあなただけの大切なねがいごとに思いを馳せてみるのも良いでしょう。珊瑚礁が広がる海の中はとても透明度が高く、星々のひかりを受けてプリズムのように煌めいています。
海中を歩むことは勿論、泳ぎながら進んでいくことも叶います。クロリスの祝福はあなたたちの呼吸や動作を助けてくれるので、溺れてしまう心配はありません。
- - - - - - - - - -
●こころのいろ
「……本当に、海の中入れるんですか?」
花の蜜を口にしただけで大丈夫だなんて、そんな魔法みたいなこと。少なくとも戀ヶ仲・くるり(Rolling days・h01025)の常識の範疇では到底起こり得ない事象に対して当然の疑問を投げ掛ければ、逃げ腰の少女に対して終始上機嫌の雨夜・氷月(壊月・h00493)は今日一番の笑顔を向けると流れるような所作で以ってその細いからだをあっという間に掬い上げた。
「変化感じないんですけ、どぉ!?」
「大丈夫、何も心配いらないらしいから!」
それ以上の問答は不要とばかり。一歩踏み出せば後は飛ぶように軽快に。
「えっなに、やっ、やだあああ!?」
哀れ少女の悲鳴は煌めく星空へと吸い込まれ、たん、と地を蹴り上げた氷月はくるりを抱えたまま一切の躊躇なく水の中へとその身を踊らせるものだから。心の準備も何も無いくるりにとっては堪ったものではなくて、なんとかその拘束から逃れんと、或いは溺れまいと手足をばたつかせて踠く、けれど。
「ほらほら目を開けて。普通に喋れてるし聞こえてるでしょ?」
「ひぇ、わっ、……あれ、息……できるし、服も濡れてない……」
瞬きをしてもぼやけることのない視界は青く澄んでいて、どこまでも広がるみなそこまで透けて見えるかのようだった。
生きている。
とりあえず、生きているのだと実感が湧いてくるまで数拍の間を置いて。
「か、抱えて飛び込む必要なかったですよね!?」
さっきまで青くなっていたかと思えば次には耳の先まで真っ赤になってぷりぷりと怒り出したくるりの表情を面白がるように声を立てて笑う氷月に悪びれた風はない。
「んっふふ、だってくるりを俟ってたら何時までたっても入れなさそうだったし。俺も初めてだけどコレ面白いね!」
早く行こうよと促しながらくるりを下ろす腕はやさしくて、いやでも、そこが優しかろうと合意がないまま海に飛び込む行為はちっとも優しくないわけで、つまりはつまり、
「もー! 反省の色がない!」
ぽかりと叩く拳なんかちっとも痛くないとばかり。咎める少女の反応を面白がって、氷月は可笑しげに笑いながらその戯れから逃れるように軽やかに水を蹴るのだった。
「はー……すごぉい。水、澄んでて、ずっと先まで見えますね」
御伽話の中を泳いでいるようだなんて。口にしてまた笑われてしまったらかなわないと喉から出掛かった言葉を飲み込みながら、くるりは眼下に広がる珊瑚の砂に続くひかりをみとめてわあ、と微かな声を溢した。
「あの光、道みたい?」
「ああ、あれが月光の導だね。あの光を追えばブルー・ムーンに辿り着いて……くるりはあいたいヒトに会える」
準備は良い? と告げる声は、きっとくるりが頷くことを知っているからこそのもの。後悔しないようにと導く悪戯な視線だって、もしかしたら緊張を解すためのものなのかもしれない。何故彼は船に乗る前にそれを教えてくれなかったのだろうか――いや、きっと。
「……氷月さん、私の会った時の顔、見たくて連れてきましたよね」
「……んは、バレちゃった?」
まったく仕様がないひと。意地悪で突拍子もなくて、振り回されてばかり。だけど。
「いっしょに行ってくれますよね……?」
恐る恐るに口にした言葉を彼はきっと否定しない。
もしも行きたくないのなら、ここで引き返すこともできるけど、と。やわく問い掛ける声にかぶりを振れば、氷月は翠を映した双眸をすうと細めて微笑んだ。
「いいよ、ちゃんと連れて行ってあげる。怖いなら手を引いてあげようか?」
「手を……?」
ほら、そうやって。冗談とも本気ともつかぬ言葉でこちらを揶揄ってくることが普段なら全く理解できないけれど。今はそれが、すこし。ほんの少しだけ、有り難かった。
「なんかされそうだからいいですぅ……」
――それを丸ごと受け取るかどうかは別として。
海の膜を通して注ぐ星の粒を浴びながらふたりはひかりの道を進んでいく。
願いを叶えるのならば、きっと。こんなふうにうつくしい夜がいい。
●天の憧憬
あるのは不思議な浮遊感とひんやりとした心地いい温度。呼吸をすることも、もちろんそこに地面が広がっているかのように歩くことだってかなう。
「すごい」
本当に花の蜜だけで海の中を自在に泳ぐことが出来るのだ。とん、と軽く水を蹴ってみれば重力を失ったかのように少女の身体は弧を描きながら海中を進み、地上では到底飛び越えられないような距離を進んだことに驚いてぱちぱちと懐音・るい(明葬筺・h07383)は目を瞬かせた。
そらの天蓋から降る月のひかりは帯のように長く深くみなそこへと続いている。
ひとや想い。場所。もう一度だけ、そのひとが逢いたかった『だれか』と繋いでくれる。年にたった一度だけ夜空が齎す光という現象も相俟って、それはまるで天の川に伝わる伝承のよう。
「(あうのは織姫と彦星じゃないけどね)」
この場合、焦がれているのはどちらの方なのだろうかなんて。少しだけ過った感傷に微かに微笑みながらるいは軽い足取りで階段を降りていくかのように海中を進んでいく。月と星のひかりを受けてきらきらと輝く水の中は夜の只中だと云うのに眩くて、知らず弾む心をそのままに。泳ぐように腕を動かせばさしたる抵抗もなく身体は前へと進み、ぴょんと跳ねてみればまるで足が尾鰭になってしまったかのように自在に海を進むことが出来ることが楽しい。砕けた珊瑚の砂に辿り着けば足元にはただやわらかな感触があって、海に抱かれているかのような気さえした。
天国も楽園も知らない。それでも。
「あるならきっとこんな場所なのかな」
仮に違ったとしても、会いたかった人にまた出会うことを今一度叶えてくれるのなら。
「……私にとってはあながち間違いじゃないのかも」
海はどこまでもやさしくて、やわく、あまく、身体を包み込んでくれている。
怖くはない。きっと――この先に待つものだって、このきらめきのように眩いものに違いないからと。るいはその瞳に憧憬を乗せ、ひかりの先へと足を進めた。
●あおに舞う
みなそこに足を進めるのはほんの少し緊張してしまう。
もしも、溺れてしまったら――でも、いっしょならきっと大丈夫。
繋いだ手を優しく引いて、セレネ・デルフィ(泡沫の空・h03434)は裾を気にするふりをして水に潜ることへの緊張を隠そうとするララ・キルシュネーテ(白虹迦楼羅・h00189)へとはにかむように微笑み掛けた。
「行きましょう、ララさん」
「……怖くなんか無いわ。ララはまだ泳げない迦楼羅だから警戒していたの」
導くつきあかりは、ああ、お前こそがきっとそうなのね。
やわらかなセレネの笑みに促されるよう、きゅっと唇を一度引き結んだララも意を決して海の中へと足を運ぶ。
「むきゅ……!」
真昼の温みを忘れさせてくれるようなひやりとした感触に一瞬肩を跳ねさせたけれど、まるで地上の延長線を進んでいるかのように難なく息ができることに気付いて閉じた瞼を恐る恐る開いてセレネを見上げたなら。ララがちょっぴりの不安を払拭できたことを知ったセレネも笑みを深めて歩を進めた。
「ふふっ、すごい。本当に濡れた感覚もない、ですね」
苦しくない。息も出来れば声も伝わる。まるで重力を失ってしまったかのように、足を一歩踏み出すたびにふわふわと体が水中に踊ることが不思議で、まるで海に優しく抱き締められているかのようだった。
「わぁ。なんて美しいのかしら」
「とても綺麗……海の中なのに、夜のそらのようです」
あぶくが弾けるたびに星あかりがちかちかと明滅する様はまるで海中に星を連れてきたかのようにさえ思えた。月のひかりを追い掛けて、宙を漂うかのように。月あかりの天使のようなその細い手を引いて、ララは先までの様子は何処へやら、常の無邪気さをすっかり取り戻して『なんだか心地よくて落ち着くわ』と弾む声を上げてセレネを仰ぐ。
月の導を進めばブルー・ムーンに出逢うことは容易いのだろう。けれどこのまま真っ直ぐにただ進むことが惜しい気がして。桜の光焔と視線を重ねた天の乙女はそっとその耳にだけ届くようにやわらかく囁いた。
「すこしだけ、私と一緒に……この煌めきを眺めませんか」
この景色をすこしでも長く、あなたとふたりじめしたいから。その言葉は先に口にした甘露よりも甘やかで、ララの胸を容易く擽るものだから。幼き雛はそのしろい頬を桜色に染めてこくりと頷きさいわいを口元に綻ばせる。
「もちろんよセレネ。寄り道は付き物……ララも、この青をセレネとふたりじめしたいわ」
「ふふ、嬉しいです」
身体が軽い。とん、と軽く水を蹴れば浮遊感と共に身体が動くのが楽しくて。いまならきっと、海の助けがあるならばと。未だ飛ぶことを知らぬ宵の翼を懸命に動かせば、ララの身体はくるりと水の世界を宙を舞うように進んでいく。
「みてセレネ、ララ飛べたわ?」
「まあ……本当……!」
ララが羽搏くたびに繋いだてのひらを通じてセレネの身体も前へ前へと進んでいく。きゃらきゃらと楽しげに咲うララが愛らしくて、『セレネも』と振り返る彼女に応えたくて。恐る恐るに翼を広げれば、まるで宵の星空をふたりで|游いで《飛んで》いるようだ。それが嬉しくて、ただ、楽しくて。こんなにも胸が踊るのは、きっと、貴女とふたりだから。
「やっぱりセレネはお月様みたい」
不意に溢れた呟きに、ぱちりと双眸を瞬かせながら見上げれば。お前の優しい笑顔が好きよ、と真っ直ぐな言葉が胸にするりと潜り込んでくるものだから、頬と耳が熱を持つのをセレネは何処かゆめでも見ているかのように感じていた。
「そうでしょうか……。……でも月で在れば、変わらず……」
あなたの傍に、いられるでしょうか。
それは憧憬にも似た。しるべなき路の途の中でみつけた春の如きぬくもりが、どうか、消えてしまいませんようにと――零れ落ちたその言葉に、ララはあまく目を細めて頷いた。
「例え月でなくても、お前がお前なら」
繋いだ手の熱が、言葉を確かなものにしてくれる。
今はまだもう少し、このまま。あおいろの只中で、ふたりの翼が大きくはためいた。
●あかいろの面影
「(綺麗だな……)」
地上の花畑とは違う。『青』という朧げな概念が今この瞬間にもくっきりと輪郭を帯びて見えてくるようだと、クラウス・イーザリー(希望を忘れた兵士・h05015)はどこまでも続く海中を何処かゆめでも見ているかのような心地で進んでいた。本来は呼吸などかなうはずもない水の中を空でも飛ぶように進んでいく感覚は何とも不思議なもので、忘れ掛けていた『たのしい』という気持ちを思い出させてくれるかのようだった。
珊瑚礁の只中を潜り抜けようと水を蹴った瞬間に、小魚たちが数匹飛び出してくる。驚かせてしまったかなと手を差し伸べれば、この海域に彼らの外敵は多くないのだろうか。『なんだかおおきなさかながやってきたぞ』とばかりに指先に集まってくるものだから、つむつむと食まれる微かな感触が擽ったくてクラウスは微かに笑みに満たぬ吐息を溢す。
「(ああ、この子達も生きているんだなあ)」
人と機械、地表を無限の戦闘機械で埋め尽くした鉄の大地。生命が限られたその場所で生まれ育ったクラウスにとって、この海は途方も無いくらいのいのちに満ちていて、眩くて。
「(何だか、すごく)」
いとおしい。その言葉があんまりにも現実離れしていて声にすることこそ出来なかったけれど――それでもこの胸に湧くあたたかな感情は、きっとそう呼ぶのが相応しいのだろう。再び水を蹴れば小魚たちは親鳥を追う雛のようについてくる。それをどこか面映く感じながらクラウスはみなそこを目指して進んでいく。
もうすぐ、もう少し。ひかりの道の続く先で、また。
「……会えたら、何を伝えようかな」
どうしてと、何度も繰り返した自問自答。この身体の一番奥深くに迸る癒えぬままの傷口は疾うに膿んで腐り落ち、最早痛みを感じることさえも出来ず、然れども確かにこの胸を苛み続けている。
――友よ。
志半ばでいのちを落とした■■■■■に、もう一度。
もう一度、君に逢いたい。
たったひとつの願いを抱いて、クラウスは月を目指し更なる深みへと身を投じた。
●真理を目指して
「(|水の精霊《レニー》の力を借りなくても、義体部分とか保護されてんだな)」
化学式では解明できない神秘を目の当たりにしながら千堂・奏眞(千変万化の錬金銃士・h00700)は感心したようにぐっとてのひらを握ってはほどいて己が身体の自由を確かめる。可能とは云え隣人たる精霊にあまり負担を掛けたくはなかったから、この奇跡が齎す恩恵は有り難い。ふたりも無事だろうかと振り返れば、すぐ後ろから華やぐ声が上がることに奏眞は密やかに安堵の息を吐いた。
「ねえねえ、これ、どうなってるんだと思う? 重要なのはお花と時期、それにこの土地そのもの?」
「なるほど。クロリスの蜜は、口に含んだ者が身に纏うものも保護するのか。実に興味深いな」
「再現環境下なら、錬金術でも同じ効果を作れるかな?」
きょろきょろと周囲を忙しく見回しながら瞳を輝かせるのが霧谷・レイ(自称 「神秘の美少女錬金騎士」・h03818)。その隣でこの海域そのものへの探究心を疼かせているのがウィルフェベナ・アストリッド(奇才の錬金術師・h04809)。側から見ていれば彼女たちの燥ぐ姿は年頃の少女のそれに違いないのだが、実際には正しく研究者としての歓びに他ならない。
わかっていた、わかっていたけれど。
「師匠は検証するか目の前の光景を堪能するのか、どっちかにしろよ……」
「何をごちゃごちゃ言っている。そら、この蜜の効果時間がどのくらいあるのか検証がてら、深いところまで潜ってみようではないか」
がっくりと肩を落とす弟子の様子などお構いなし。我が物顔で海中を征く師の姿にやれやれと先とは意味の違う溜息を吐きながら奏眞も緩やかに水を蹴る。
自由奔放な師匠には困ったものだけれど、母なる海に包まれた中で過ごすレニーも、常に共に在る他の精霊たちも楽しそうに水中を泳いでいる様子は奏眞にとっても心地良いものであった。この海に満ちた神秘性と彼ら精霊はきっと相性がいいのだろう。それだけでも来た甲斐があったと思えば、多少のウィルフェベナのやんちゃにも目を瞑れようと云うもの。
「海の中に居ながらも星空の中を歩んでいるかのようだな」
この世のものではないくらいに煌びやかな海中は幻想的と一言で括るには惜しいほど。月の光とすべてのあおいろが混ざり合ったかのような世界が醸し出す神秘性に、ウィルフェベナは『実に面白い』と微かな感嘆を溢す。
「うおお、すごーい! こんな風に海の中で歩けるなんて、きれーい!」
レイが弾む声を上げるたびにぷくぷくとあぶくが浮かんで、そのひかりの明滅に誘われるように寄ってくる小魚たちが戯れついてくるのが楽しくて。『すごいね!』と声を上げれば一瞬言葉を詰まらせた奏眞が頷いてくれることにレイの笑顔がますます深くなる。
「こんなにお魚を近くで見るのはじめて! 触っても大丈夫なのかな?」
こんにちは、とゆびさきを遊ばせたなら挨拶を返してくれるかのようにあまく啄んでくる感触が擽ったい。奏眞くんも、と促せば戸惑うように伸びた義腕に一際ちいさな魚が寄り添う姿がなんだかへんてこで、くすくすと笑えば奏眞はそっぽを向いてしまう。
「まったく……少しはこの光景に感動を覚えろ、このバカ弟子が」
「悪かったな、こういうのに疎くて!?」
折角友人が構ってくれているだろうがとでも言いたげな師の言葉にむっと唇を尖らせるけれど、それで動じてくれるような彼女ではない。ゆらりと水の流れに合わせるように揺れた奏眞の髪束をつんと付き、ウィルフェベナは目を眇めて未だ成長の途にある弟子を揶揄うように『お前の今後の課題だろうな』と笑った。
「……レイ、師匠がうざかったら話半分で聞くだけでも大丈夫だからな?」
「んー? 別にうざくなんかないよ、ないですよ?」
ちょっと風変わりだけれど、彼女から悪意は感じられない。だから平気だと笑えば方や奏眞は肩を竦め、方やウィルフェベナはふふんと鼻を鳴らす。まったくちぐはぐな師弟のありかたが可笑しくて目を細めれば、不意に。それまで終始尊大な様子であったウィルフェベナが真剣な眼差しを未来の錬金術を担う子どもたちへ向けて厳かに唇を開く。
「レイ、奏眞。この先にあるものの伝承に、興味はないか?」
それはいち錬金術師としての。或いは先達としての優しさだろうか。知った上で何かを願うのであればと問い掛けるその言葉に、少女は少しだけ考え込む所作を挟んだのちに友の師を仰いだ。
『会いたいひとに、また会える』。
居ない訳ではない。居ない訳がない。取りこぼしてしまったものはひとつやふたつではない。それでも。
「でも……ううん、いいや」
居なくなったひとにはもう会えない。レイにとって過去は振り返るだけのものでいい。この夜に奇跡があったとしても、叶ってしまったらこころのいちばん弱い部分が曝け出されてしまいそうだから。
「代わりに、折角だしここでしか見れない景色をみつけたいな!」
「ふ。……そうか、それも良いだろうな」
揺るぎない少女の意思を垣間見て、少年は少しだけ胸の奥にちりりとした痛みを感じていた。
「(…………オレには、縁遠いことだな)」
ひとつ、ふたつ。幾つもの想いを抱いて、智の探究者たちは海底を目指し進んでいく。
どんなかたちであったとて。たった一夜のあおいろはきっと、分け隔てなくすべてを優しく包み込んでくれるはずだから。――だからどうか、怖がらないで。
●うたかたに揺れ
煌めく青の色彩そのものに抱かれている。思わず零した息があぶくとなって、星のひかりを反射してちかちかと瞬く様が網膜を突き抜けて頭の中に直接投影されているかのようだった。
これが、青の扉のさき。クロリスの祝福が見せてくれる唯一の光景を目に焼き付けるよう、シルフィカ・フィリアーヌ(夜明けのミルフィオリ・h01194)は水中を舞うように翼を一度大きくはためかせた。
ゆりかごに揺られた幼き日の記憶など勿論ありはしないけれど。
「(このまま眠ってしまえたなら、優しい夢が見られそう)」
そんな『もしも』を期待してしまうくらいには一夜限りの奇跡を惜しいと思ってしまう。それほどまでにこの海はどこまでもあおく澄んで、どこまでも静かでうつくしい。ほんとうに海の中にいるのだと実感するには十分なほどに周囲はたくさんのいのちに満ち満ちていた。
珊瑚礁の中からこちらを伺うように顔を出した小魚たちがついてくる。地上では見られないような鮮やかな色彩を持つ彼らと戯れ泳ぐことも楽しいけれど、『またね』とちいさく手を振って別れを告げて。月のひかりを辿っていけば、シルフィカの身体はやがて珊瑚の骨――砕けた星のかけら、白い砂の上へとやわらかく受け止められた。
見たかったものも、逢いたかったひとも。いとしい記憶たちを失った今のシルフィカにはわからないけれど、でも、それでも。
「(心の何処かで、期待している)」
もしも、思い出せなかったとしても、この胸の奥底に眠る『かけら』に出逢えるのだとしたら。
「……ねえ、ブルー・ムーン」
空っぽのわたしに、あなたはどんな夢を見せてくれるのかしら。
もしも記憶が痛みを齎すものであったとしても。こんなにもうつくしい世界が見せてくれるものが、痛ましいばかりのものであるはずがない。少女の呼び掛けに応えてくれたのだろうか、深く、みなそこの奥深くで。ちかりと一際鮮烈なあおいろが煌めいた気がして――シルフィカは祈るように胸の前で組んだてのひらを握り、さいはてへと向かい翼を広げた。
●さいわいあれと
爪先をひたりと浸して海の中へと進んでいけば花畑から地続きのように歩いていくことが叶う。ゆっくり、けれど一歩ずつ真っ直ぐに。アンジュ・ペティーユ(ないものねだり・h07189)はみなそこを目指しながらひかりの道をゆったりとした歩調で進んでいた。
「今は眠る時間かな?」
真昼であれば元気に泳いでいるであろう小魚たちは今は少しのんびりとした動きで、水が静かに揺れるままに身体を海に委ねていて。手を伸ばせば応じるようにちいさな口をぱくぱくと動かすのが可愛らしくて、ふ、と微かに吐息を漏らしてアンジュは魚たちに『おやすみ』を告げる。
「ここもとっても綺麗な景色」
地上から見たあおいろだってうつくしかったけれど、水中から星空を見上げる機会なんてそうありはしない。普段から好奇心の赴くままに色々な場所に足を運んでいるけれど、こんなふうに静かに海を堪能することはあまりなかったかもしれないな、なんて思えばこの一瞬を永遠に切り取ってしまいたくなる。
「綺麗……」
月の光を追いかけて、底へ、底へ。
ゆらめく水面を見上げれば降り注ぐ星あかりが幾重にも反射していて、まるで宇宙に抱かれているような気にさえしてきて。水晶体を通して脳神経の隅々まで。カメラがなくたって瞼を閉じたら何時でもこの光景が思い出せるようにと、アンジュはひかりの粒のひとつひとつを目に焼き付けながらみなそこの奥深くへと潜っていく。
「(あたしの願い。願いかぁ……)」
『ひとの|感情《空想》』は幾つも手に取ってきた――けれど、自分自身の願いはどうだろうか。
ねがいのかけら。いのりのかけら。幾つもの美しい宝石たちを取ってきた手を握り締めてアンジュは咲う。
「(あたしの願いは、きっとあたしを生み出した人の願いなんだ)」
たくさんの|表情《いろ》と、たくさんの感情を受けた今だからこそ感じ取ることが出来る。
――皆に幸あれ。
魔法は自身のてのひらのなかにあるのだからと。アンジュはそっと、みながそうあれるようにと願うまま密やかに微笑んだ。
●きみとあゆむ
見渡す限りのあおいろは、クロリスの花畑とはちがったあたらしい『あお』を教えてくれる。
「ここに眠っているんだね」
みんなの願いをうつしてくれる、優しいおつきさま。
天深夜・慈雨(降り紡ぐ・h07194)はとくとくと鼓動が高鳴っていくのを感じながら海中を揺蕩うように進んでいた。苦しさを感じることもなく水の中をこんなにも自由に動けるなんて。絵本の中に出てくる人魚になれたような心地に揺られ、慈雨はほのしろい頬を淡く染めながらくるんと海の中でスカートの裾を海月のように翻す。
「これもクロリスに貰った魔法のおかげ……、……あ、珊瑚礁!」
砕けた星の砂のなかに群生するそれらはまるでみなそこの花のよう。たくさんのいのちの止まり木になっている鮮やかな珊瑚たちを見とめ、慈雨は胸に抱えた愛らしい一輪にその景色が見えるようにと身体ごと傾けて、魚たちがびっくりしないように緩やかに水を優しく蹴りながら進んでいく。
「君もはじめて、見た?」
慈雨に選ばれたクロリスは言葉を話せないけれど、もしかしたら喜んでくれているのかも。てのひらの中でゆらゆらと花弁を揺らす花が散ってしまう気配はなくて、少女はほっと胸を撫で下ろした。
「夜明けまで……まだ時間はあるよね」
あなたが未来のあなたにいのちを託してしまうまで。この魔法は一夜限りの特別だから。
「いっぱいのあおの世界をみてからそこへ行こうね」
月のひかりが呼ぶ方へ。あなたたちが繋いでくれた奇跡を、一緒に見るために。可憐な花がくしゃりと潰れてしまわないように、少女はひかりの道を静かに進む。
やがてましろの砂が次第に近付いて、慈雨とクロリスはふわりとみなそこへとたどり着く。母なる海に抱かれながら、慈雨は恐る恐るに顔を上げてひかりの先へと目を凝らした。
「(そこにあなたはいるのかな。あえるかな、……あいたいな)」
今はただ、祈るようなきもちだけ。
どこまでも澄んだいのりに応えるように。みなそこの奥深くが、きらりと一層強く、あおく煌めいた。
●なまえ
折角だから海底まで彼女を乗せて泳いでいきたい。だから、相応しい姿に化けてみたかった。
「うーん、やっぱりちょっとへたっぴだよねぇ……」
それはわだつみの戦車を牽く海馬の姿の筈だった。月夜見・洸惺(北極星・h00065)の割れた鬣は鰭状となり、下半身は魚のそれと見紛うほど。
そこまでは良かったのだけれど。
「……本当の姿の感覚が抜けてなかったかも」
前脚は四本のまま。翼も仕舞い忘れてしまったちぐはぐな姿になってしまった。化け術も早く上達するといいね、なんてくすくすと笑う集真藍・命璃(生命の理・h04610)の言葉に、風変わりな海獣は気恥ずかしげに鼻を鳴らしながら目を細める。
「でもでも、今は上手じゃなくてもこれからウマくなるよ」
「ふふっ、そうだね。でもきっと四本の脚も、翼もチャームポイントだよっ」
伝承通りのすがたじゃなくたって、あなたを乗せて泳ぐことは出来る。
さあ、夜の海中散歩へと出掛けよう。そこには見たこともないいのちのいろが、たくさん溢れているはずだから。
「すっごーい! お魚さんがこんなに近くにいるよっ」
色とりどりの魚たちが目の前をゆっくりと泳いでいくのがなんだか不思議だ。手を伸ばせば人見知りをしないらしい小魚たちが挨拶をしてくれるようにちょんちょんと口を寄せてくるのが擽ったい。背中から命璃の燥いだ声が上がれば洸惺も嬉しくなって思わず短く嘶く。
「あ、カニさんも……」
「ほんとだ! カニさんもいるねぇ」
波間を潜るように降り注ぐ月光はまるでひかりのカーテンのようにも見えて、ゆらゆらと揺らめくたびに自分たちの姿も海の中に浮かび上がっていくような心地がした。
「……命璃お姉ちゃん。美味しそうなんて言ったら、水族館の時みたいにまた逃げられちゃうよ?」
すこしばかり食いしん坊な彼女が、ひょっとしたらこの子たちにもそんなことを言ってしまうんじゃないかなんて。振り向けば一瞬ぎくりと肩を跳ねさせた命璃は取り繕うようにぶんぶんとかぶりを振って否を示す。
「もう美味しそーなんて溢しちゃう命璃ちゃんじゃありませんとも!」
「ふふっ。そうだね、ごめん」
命璃はお姉ちゃんなんだもの。ちょっぴりいじわるだったかな、なんてはにかむ洸惺の背の上で、命璃はえへんと胸を張って見せた。
「皆は月になにを願うんだろう。皆のいのりって何なのかな」
会いたいひと。いつか訪れた景色。ひとに依って心の拠り所にしているものは様々なのだろうけれど、何かに縋らなければ生きていけない在り様を見ていると時々疑問に思うのだ。
「僕は皆が幸せだったら、それで良いかなぁ」
にんげんは脆い。おろかで、よわくて、だからこそいとおしい。彼らの生き方は酷く不可解で、ひとならざるものである洸惺は大変そうだなあと思わずにはいられない。
「いのり。私のいのりはねぇ」
そんな洸惺の疑問を他所に、少女はほんの僅かな憂いを乗せて海のさいはてを見詰め声を落とす。
このいのちは疾うに尽きた。ねがいはのろいへと変わり果て、ああ、でも、それでも。こんな風にたくさんのきれいな景色を見て、知って。たくさんのひとや動物たちと出逢って、触れ合って――それから。
「いつかお父さんに報告するんだっ」
生命は世界で一等尊い宝物。
それが私の名前。お父さんがくれた、はじめての宝物だから。
「……そっか」
命璃の表情は見えない。それでも彼女が、彼女の愛する父が愛しんできたものたちのうつくしさは伝わっているから、洸惺が彼女を笑うことなどありはしない。
「えへへ、一緒に色んな景色や人や動物に出逢っていこうね」
「うん!」
これからもふたりで一緒に。どこまでも続く世界の果てに、そこに息衝く人たちに会いに行こう。
もしもあなたが迷ったときは、僕が必ず導いてみせる。
少女の想いごと乗せて、翼ある海馬はひかりの奥へと飛び込んでいった。
●うつろい
「うわー沈むー!!」
海のしじまに響き渡ったエオストレ・イースター(桜のソワレ・h00475)の賑やかしい|春告の声《悲鳴》にうとうとと揺られていた小魚たちが飛び上がる。
「なっ、何だよ卯桜! いきなり叫んだりして、驚くだろう」
「だってだって! 海の藻屑になっちゃ……、……ならない!」
隣を泳ぐ咲樂・祝光(曙光・h07945)が思わずその名を口にするも、エオストレにそれを咎める余裕はない。くるしいくるしいと首が締まったかのようなジェスチャーを交えるけれど――やがて気付く。頭から爪先まで水の中に沈んでいるはずなのに、祝光の声はよくよく長耳に届いているし、呼吸のたびにぽこぽことあぶくこそ上がるけれどちっとも苦しくなんかない。
「ねえみて、祝光! 僕、水中でもへっちゃら!」
「ああ。大丈夫、俺達にはクロリスの祝福が……こら、うろちょろするな」
ひとつ安心してしまえば先の様子は何処へやら。エオストレがぴょんぴょんと海中を跳ね回るたび、彼の喜色をそのまま映したかのように薄紅色の花弁が舞った。その変わり身の早さにちいさく溜息を吐きながら祝光は漂うさくらいろを追い掛けるように水を蹴る。
「これが花の蜜の効果……すごいね」
「そうだな、本当に伝承通り……、っ!?」
がくん、と身体が思い切り傾く。重心がすべて片腕に回ったような感覚に体制を崩しかけたなら、エオストレが今まさに勢いよく自分の腕を掴んだことを知り祝光は何事かと目を見開いた。
「うろちょろするなとは言ったが、腕を組めとは!」
「いいじゃんべつに!」
まったく陸でも海でも忙しない。エオストレの突拍子も無い行動はいつもの事だけれど、どうもおかしい。水中では感覚が少し鈍るけれど妙に腕を掴む手は力んでいるし、目線も若干ぎこちない。
「……君、もしかしてまだ不安なの? 溺れないか」
間。
「べ、別に……不安があるとかそういう訳じゃないし?」
目が合わない。声は若干震えているし、歯切れの悪い言葉が示すものはきっと肯定なのだろう。けれど。
「あ! みて! イースターみたいな魚がいるよ! あっちには珊瑚がたくさん!」
クラッカーを弾けさせた紙吹雪みたいな小魚たちはたいへん|祝祭《イースター》らしいし、星あかりを受けてきらきらと輝く珊瑚礁はエオストレの目と心をたいそう楽しませた――いや、いやいや。
「話を変えたな?! ……こら、ミコト!」
友が潔く話をすり替えたことを咎めるのもそこそこに、食いしん坊が小魚たち目掛けて飛び出そうとするのを慌てて空いているほうの腕で捕まえる。右も左も賑やかで思っていた夜とは違うかもしれないけれど、何時ものことかと微かに笑えばそれを見上げていたエオストレも上機嫌に笑みを咲かせた。
月明かりを追って、珊瑚の骨が砕けた白い砂の底を歩む。
「俺は……龍王になりたいんだ」
ねがいはひとつ。そう成れたなら自分の大切な家族に誰も手出しなど出来ようもないからと。己が未熟を噛み締めれば苦さが胸に湧いてきて、思わず眉根を寄せてしまう。
「……エオストレは?」
彼はどちらかと言えば『叶える側』の立場なのかもしれない。けれど、ひとならざるものとて願いを抱く資格はあるはずだと。昏い気持ちを振り払うようにかぶりを振って腕を組んだままの友を仰げば、エオストレは少しだけ寂しげないろを双眸に乗せてはにかんだ。
「願い事? 僕は……皆がハッピーイースターならそれでいいよ」
本心だ。でも、本当はそれだけじゃない。
本当は――自分にしかできない、自分だけの『なにか』を見つけたいのかも。だけど、そんな風に思ってしまうのは何だか自分らしくない気がして。いたみを隠すように咲えば、君の憂いだって拭い去れるような気がしたから。
「あっちにもキラキラがある、行ってみよー!」
「お、おい! エオストレ!」
手を引いて、引かれて、ひかりを辿る。
その一瞬に救われたような気がして、祝光は眩しげに友を見詰めその背を真っ直ぐに追い掛けた。
●うつくしきもの
「成る程成る程!」
ちゃぷんと水に足を浸した感覚はあるのに濡れた感覚までは肌に伝わってこない。躊躇いなく海の中へと身を預けたナギ・オルファンジア(■からの堕慧仔・h05496)は五感のすべてに触れる未知へ胸を躍らせながらひかりの道を歩み始めた。
「空気の透明な膜、へぇ、面白いなぁ」
てのひらを翳してみれば薄く全体に膜が張っていて、薄い空気の層が肌や衣類を守ってくれているのが分かる。日傘を差したまま身を翻せばふわりと広がった服の裾を仲間だと思ったのか、薄ぼんやりとあおいひかりを纏った海月たちが側に寄って来てくれることが楽しい。
「お洋服も濡れませんし、便利ですこと。……ふふ。あなたたちもブルー・ムーンをお探し?」
彼らの見目は愛らしいけれど、触れてしまわないように。ごきげんよう、と傘をくるんと回してみせれば海月たちも細長い触腕をゆらゆらと揺らして応えてくれた。
出来るだけ下へ。深く、深みへ。
昏く静かなみなそこの方が馴染み深いし心地よい。己が膚が淡くひかりを宿してしまうのを月あかりのせいにして、そろりと砕けた星の砂に足をつける。
「(身体が軽い)」
これもクロリスの祝福のお陰だろうか。大きな珊瑚礁も軽く海底を蹴るだけで容易く飛び越えてしまえる。深海に住まう魚たちがひかりに釣られて寄ってくる姿に挨拶を交わしながら歩めば酷く懐かしい心地がして、ナギはひかりの中でいっそう煌めく黎明の瞳をあまく細めた。
「(ナギはねがいごとを持ち合わせておりません)」
そんなものを抱けるほどの自我は未だ微睡の中。それでも――人の夢の残滓には興味がある。御伽話を信じて縋って海底に身を投げた者たちのねがいは、いのりは、一体如何様なものであるのか。
常ではない月が満ちるとは、一体どんな光景なのだろうと。いのちあるものへの好奇心を胸に、嘗てそらに座した娘はひかりの満ちる方へと緩やかに進んでいった。
●やくそく
ざぶんと勢いよく頭から海に潜ればそこには地上とはまた違ったうつくしいあおいろの世界が広がっていた。
「(水の中でこんなにも自由でいられるなんて、クロリスってすごいな)」
肺に酸素を溜めずとも溺れず、水圧に潰されてしまうこともない。こんなにも自在に水の中を游ぐすべは水無瀬・祈(五月雨・h06808)の知る御業の中でも極致に等しいものであり、それを容易く叶えてくれる一夜の神秘に驚くばかりだった。
「この色は……カイヤナイト、かな」
密かに集めた宝物。深い青の世界に海の石を思い描きながら、祈はほんの少しだけ安堵していた。
――いつか、|あのいろ《パライバ》の海を、あなたと。
耳の先まで赤く染まった不器用な笑顔と約束した海の色と今眼前に広がるこのあおいろは趣が異なる。その『いつか』は、彼女と分かち合いたかったから。
月のひかりを道標に水を蹴る。
水無瀬の一族にとって水は最も親しいものであり、祈にとってもそれは例外ではない。息継ぎを気にすることなく水と遊ぶことが出来ることがただ楽しくて、魚たちと並んで泳げば彼らとも友達になれたような気がして知らず祈の口元は笑みの形を描いていた。
珊瑚礁の合間を潜り、塒へ向かうイルカたちに手を振って。ひかりの道へと再び戻れば、やがてましろい星の砂が見えてくる。
「ブルー・ムーンを見つけたら、あいたかった人に会える、か……」
思い浮かぶ人がいないわけではない。けれど自分がどうしたいのか、どうすべきなのかを迷っている。迷いは己が未熟さが故のものであると分かっているからこそ、煮え切らぬ心に焦れてしまう。
「(青い月を前にしたら、俺の心も決まるだろうか)」
今はまだ答えが出ない。そこに正しさなどはじめからないのかもしれない。それでも前へ進むことを止めないのはきっと、もうひとつの家族が帰る場所を自分に与えてくれたから。
あおく、あおく。みなそこを進んださきに、一層輝く澄んだ気配が直ぐそこまでに近付いていた。
●垂る光彩
「おお、海中を歩いて行けるとは本当にスゴいな……!」
本当に海の中でも呼吸が出来ている。音さえ包み込んでしまう筈の潮の中でも互いの声が届くことに驚きながら、トゥルエノ・トニトルス (coup de foudre・h06535)は軽い身体の感覚を楽しむように緩やかに水を蹴って進んでいく。
「クロリスの祝福、様々……と云ったところだなァ」
人工の海はひとの目を楽しませるに充分ではあったが、ほんものの海はさかいめはおろか果てさえ見えない。いつかふたりで訪れた水族館にいたいきものたちの姿はトゥルエノをたいそう楽しませたけれど、あの時とはまた違った感情が胸の奥底から湧いてくるのをあどけない貌に喜色として浮かべ、少年は同意を求めるように緇・カナト(hellhound・h02325)を仰いで小首を傾いだ。
「景色だけではなく、海を感じられるような心地だな」
「ふうん?」
そういえば水族館に連れて行けとせがんだのもトゥルエノからだったか。自分に合わせてくれるのは良いが、主の活動域で遊ぶのも一興だと――あの時も唐突でカナトは目を丸くしたものだけれど。
「(精霊サマ的には人間の施設と大差ないとか言うのかと思っていたけど)」
存外彼もひとらしく、五感でせかいを感じ取ることを尊く思えるものであるらしい。
未だ互いに知らないことも多いけれど、こうして真新しい景色を共にするたびに『かけら』を拾い集めていけるような気がして、それも悪い気はしないものだと青年はそっと目を伏せる。
「海の生きものとして過ごしてみたくなるような気持ちも何となく分かる……ような気もする!」
「生まれ変わったら海の生きものに成りたい、なんて人間特有のモンかと思っていたゼ」
トゥルエノは雷を司るもの。であれば水中で活動するなどと云う機会はほんとうに稀なことに違いないのだろう。すこしだけぼんやりした様子の小魚たちが来訪者のすがたに寝ぼけ眼を向けながら、ふわふわと海中を漂うように珊瑚の塒から顔を出してくるものだから。ぱちりと目を瞬かせたトゥルエノは『主も見ろ!』と声を期待に弾ませる。
「住む世界の違うものたち……異文化交流というヤツだな!」
「そういうモンか」
色とりどりの魚たちが自分の何倍もの大きさがあるふたりをおそれずに近寄ってくるのも、躊躇いなく彼らに手を伸ばす主も。物珍しげに瞳を輝かせながら未知と触れ合うその姿は幼い子どものように無邪気で、何だか毒気を抜かれた気分だとカナトは人知れず微かに笑った。
陸に住まう者だからこそ海底を目指したくなる、そんな想いもあったのかもしれない。
「(……実際は誰もいないだろう所に行きたかったのかもしれない)」
けれど、月のひかりが導く先に広がるものが齎すものはきっと単なる孤独ではないのだろうことも、分かる。分かるからこそ簡単に願いを口にすることは憚られて、ほんの少しだけ先に進むことを躊躇ってしまう。
「この先に眠っているのであろう蒼い月に、我が望むことは特にないけれど……」
そんな胸中を見透かされてしまったのだろうか。主はどうか、と。水の中でだけ重ねられる同じ高さの視線に射抜かれてカナト僅かに息を詰まらせる。特別見たかったものがあるわけでもないが、望みが全くないと言えば嘘になる。こちらの心をすべてさらってしまうようなうつくしい青雷のいろから、ほんの僅かだけ目を逸らして。
「……。……水底の青い月に興味があった。今はそういうコトにしておいてくれ」
辿り着いたその先で青く照らされたその時に。きっと、今一度考えるだろうからと――告げる言葉にトゥルエノは目を細め、『気にすることはない』と笑う。
「主と景色が共に見れたら其れが良いのだ」
ねがいのあるなしなど些細なこと。
共に見上げる月にこそ価値があるのだと、幼き雷獣はそっとカナトへ手を差し伸べた。
●君と紡ぐ
星のひかりと海中のきらめきが祭那・ラムネ(アフター・ザ・レイン・h06527)の瞳に反射して、プリズムのようにちかちかとひかりの道に微かな虹を落とす。
「まるで夢の中にでもいるみたいだ」
世界は広くて。本当に、本当に広くて。
もう歩くことのない通学路や、施設の塀の中。花屋の軒先から見える景色と、それから――指折り数えれば終わってしまうほどのラムネの『これまで』をあっという間に塗り替えてしまった。
子どものころに憧れた冒険譚の主人公はこんな風に胸を躍らせたのだろうか。とくとくと胸の鼓動が高鳴って、叫び出したいほどの衝動を抱いて。今は自分が物語の続きを描いているのだと思えば緩んでしまう頬を抑えきれない。
「カエルムさん、泳いでいこう」
首から下げたあおい石が、星あかりを映して微かに揺れる。そらを愛した彼は大海を泳いだことはあるのだろうか。もしかしたら、あおい海を眼下に大空に翼を広げていたのかもしれないな、なんて。想像を巡らせればうれしさばかりが胸に次々と湧いてくる。
のんびり歩いていくことも出来たけれど、折角の海の中なのだから泳いでみたい。水泳の経験は授業で受けた程度のものだったけれど、ラムネは水と仲良くなることが得意だった。直ぐに泳げるようになった幼いころの自分を見て、クラスメイトも先生も目を丸くしていたっけ。
ひとの脚を魚の鰭のようにしならせながら、星の海と見紛うほどの煌めく魚の群れに混じって游いでいけば元々自分は海の住人であったかのような気さえする。
この海域にひとを襲う脅威はほとんど存在しないのだろう。身を守るための毒を持つ海月や貝を幾つか見掛けるくらいで、殆どはおとなしい小魚たちが思うまま潮の流れにのんびりと身を任せていた。煌めく珊瑚礁の住まいはどんなつくりをしているのだろう。ああ、住人たちを起こさないように慎重に! 月のしるべを遮るようにどっかりと座った海亀の甲羅をこつこつとノックしてみれば、緩慢に目を開けたご老体がのそりと道を開けてくれるのに、ラムネは思わず笑ってしまいながら『ありがとう』と手を振って応えた。
ひかりの道を游ぎながら、指先で軽く輝石に触れる。
「俺、ブルー・ムーンに願うことは決めてるんだ」
もう一度、会いたいひとがいる。
夢の中ではない場所であなたに会いたい。
あおいろの世界を、水の中を翔けていく。不意に頭上でゆらりと大きくゆらめいた影に顔を上げれば、まっしろな鯨の長い長い航海を見た。彼も何処かへ、何かを求めて旅をしているのだろうか。水面に浮かぶ巨大な姿とふたつの影が重なって――ああ、まるで竜みたいだなんて。ラムネは煌めく瞳を細め、果てへ、果てへ――青い月が待つその先へと進んでいった。
●みなそこに咲く
呼吸ができると言われていても、実際に飛び込もうとなると己の今までの常識がほんのすこしだけ邪魔をする。躊躇うように視線を伏せた神花・天藍(徒恋・h07001)の様子を見れば、彼が何かを憂いているのではないかと継歌・うつろ(継ぎ接ぎの言の葉・h07609)は恐る恐るにその横顔を覗き込んだ。
「天藍さん、少し、考えごと……?」
もしかして、ひょっとして。自分を怖がらせないために気丈に振る舞ってくれているけれど、彼だって水に潜るのは不安なのかもしれなくて。それをそのまま口にしたなら、きょとんと目を丸くした天藍はややあって、ふ、と吐息を溢して微笑むとかぶりを振って否を唱えた。
「怖いのではない。……我が身に纏うは冬の冷気だ」
冬はすべてのいのちを氷の下に覆い隠し、花咲きえることも叶わない。もしもこの力が水を凍らせ、小魚たちを怖がらせてしまわないかと戸惑っていたのだけれど。そっと波間にてのひらを浸してみても天藍が身に纏う冬が海水を凍らせてしまう様子は無くて、クロリスの花が齎すさいわいの恩恵にちいさな安堵を溢せばうつろの表情も柔く綻ぶ。
「(……やっぱり、やさしい人)」
自身は命を散らすものであると彼は言う。だけどきっと、ひとを遠ざけようとする物言いは彼の優しさからくるものなのだろうと。知れば胸にはあたたかな温度が宿るようで、少女はちいさく『よかった』と溢してはにかんだ。
「うつろは大丈夫か?」
「わたしは……えっと、ね」
海に潜るなど中々出来る経験ではない。もしもおそろしいと感じたり不安を覚えたりしているならば、無理をせずにゆっくり進めば良いと小首を傾いで問うたなら、天藍の心配を他所にうつろの頬は好奇心と喜色でほのあかく染まっていた。
「海って、じっさいに来たのは、はじめてだから」
絵本や図鑑から導き出した想像とはまるで違う。あかねいろの瞳に映る雄大な水のせかいはどこまでも広くて――胸に満ちる情動を、幼き災厄はすべてを言葉にして伝えることは出来なかったけれど。ぱたぱたと燥ぐ魚のように足を游がせればそれだけで少女の興奮は十分に伝わったのか、天藍もやわらかく目を細めそれに応えた。
「……おぎょうぎ、わるい?」
「いいや。……さあ、往こうか。海の花畑を見に」
深く、深くへ潜っていく。
からだが重さをなくしたみたいに水の中を自在に動けるのは不思議な感覚で、独特な浮遊感に心も弾むよう。
「海の、お花……」
「ああ、海の中にも花は咲く」
正確に言えば花そのものではないけれど。白い砂から伸びゆく色とりどりの珊瑚たちをてのひらで指し示せば、その煌めきにうつろがはっと息を呑む音が聞こえ、真っ直ぐなこころの表し方を目の当たりにした天藍の胸もすこしだけ温度を取り戻したかのような心地がして眩しげに目を細めながら頷いた。
「海底で咲く珊瑚はまるで花のようであろう?」
「さんご……これが、さんご」
たくさんのいろ。花のいろよりも鮮烈な、まぶしいいろの煌めきに目を奪われる。地上で見る花畑だってとてもうつくしかったけれど、本来ならひかりの届くことのないみなそこに咲く彼らのことを、とてもきれいだと思った。
「海の中にも美しき世界は広がっている」
年に一度の奇跡が齎すもの。こんな機会でもなければ見られぬものだと告げる声に少女は頷く。
きれいなもの。しらないこと。からっぽのうつろに、見返りもなくたくさんのことを教えてくれる彼はやっぱり優しくて。ありがとうと口にしたならもしかしたら彼は照れてしまうのかもしれないけれど、それでも伝えずにはいられない。
「天藍さん、たくさん、知ってるね……すごい、ね」
「……うつろも今知ったろう?」
しらないことは、これから知れること。
ぱちりと少女の瞳が大きく瞬いたのを見て。雪解けの陽を浴びたかのように、天藍は可笑しげに声を上げて笑った。
●徒夢
揺らめく水面から身を浸せばひやりとした温度だけが膚に伝わるようだった。
「息が、出来る」
灰と硝煙に満ちた暗がりよりもずっと呼吸がし易いことに気付いて、夜鷹・芥(stray・h00864)は物慣れぬまま臓腑いっぱいに澄んだ空気を満たす。面が無いだけでは無い、これこそがクロリスが齎すさいわいそのものなのだろう。
「(魚にでもなったみてぇだ)」
夜闇を切り抜いたかのような影が落ちてきたことに気付いた小魚たちが怯えた風もなく近寄ってくることに芥は数度瞬きその姿を視界に留めた。
「……なぁ、お前達から俺はどう見えてる?」
青色に黄色い尾鰭を持つその姿は何時か何処かで名を聞いたことがある気もするが、思い出せない。ただ、うつくしい姿に反して身を守るための毒を持っていることが自分好みだと感じたんだったか。朧げな記憶を辿りながらゆびさきを遊ばせれば、くるくると踊るように戯れてくるのはこの海域で彼らに大きな脅威がないことの証左のように思えて、青年は微かに目を細めた。
月光の道を辿り、深く、深く、みなそこへと降りて行く。
「(此の世界を自由に歩けるのが一夜の魔法で良かった)」
もしこの奇跡が永遠であるならば。その居心地の良さに、ずっと抱かれて沈んでしまいそうだった。
「(あなたは海が好きだったろうか)」
闇の似合わぬ男だった。
殺しに似つかわしく無い陽のひかりを抱いた、眩しいひとだった。
「(魚は……ああ、釣りは好きだと言っていた気がする)」
彼は生き方を教えてくれた。それなのに――夜闇の中から、掃き溜めの中から掬い出してくれたあなたのことを、殆ど知らない。あんなにも近くにずっと居たのに、自分は彼のことを知ろうとさえしていなかったのだと云うことを失ってから思い知らされる。
この景色を、あおいろを、あなたに見せたかった。
「きっと嬉しそうに笑うんでしょう?」
面影だけが今も網膜に焼き付いて離れない。
たったひとつのしるべを抱いて、芥はひかりの先へと手を伸ばした。
●ひかりに揺蕩う
すこしだけ、こわい。
やさしいひまわりの面影がラデュレ・ディア(迷走Fable・h07529)の脳裏を掠めるけれど、今宵の海にはひとりきり。――でも、大丈夫。『お友達になりたい』と言ってくれた彼女が引いてくれた手のあたたかさは記憶にまだ新しくて、彼女と共に進んだあおい海だって、とてもやさしいものだったから。
「……っ、行きます……!」
怖がるのはここでおしまい。
ぎゅうっと目を瞑れば、水飛沫にびっくりすることだってきっとない。意を決して海の中へと身を躍らせれば、ぱしゃん、とちいさな水音が響く。
「……!」
知らず呼吸さえ止めてしまっていたことを思い出して思い切り息を吸うけれど、肺に満ちるのは海水ではなく澄んだ夜の空気だったことに驚きぱちりぱちりと目を瞬かせたなら、世界は磨り硝子越しのそれではなくて。どこまでも透き通ったあおいろの続きであることを知り、少女は声にならぬ感嘆を上げてきょろきょろと周囲を見回した。
「ほんとうに目も見えて、息も出来ています……!」
てのひらを見つめてみれば薄い空気の膜が自分を守るように包み込んでいるのが分かる。手足に水の抵抗は無く、まるで水の只中に浮かんでいるかのようだった。
「これがクロリスの加護、でしょうか?」
なにか言葉にできない、超常のものから授かった恩恵を享受しているような不思議な心地だった。
先までの不安は何時の間にかどこかに行ってしまって、あとには眼前に広がる夜の海へ向かうきらきらとした感情だけが残る。ラデュレは知らず綻ぶ花唇を覆うことも忘れ、魚たちに倣うようにみなそこを目指し潮の流れに身を任せた。
ゆらゆらとたなびく星あかりが線を描くようにみなもから降り注いでいる。ひとつ、ふたつ。数えきれないほどに落ちてくる星のひかりは水が揺れるたびに幾重も折り重なって、ラデュレのしろい輪郭をやわらかく照らしていた。
「海中には素敵な世界が広がっているのですね……」
海はただそこに在り、静かにいのちを受け止めてくれているのだと知った。月のしるべの先に待つブルー・ムーンのすがたを思い描けば期待に胸がさざめいて、奥底から湧いてくるこころが溢れてしまいそうなほど。
自分が失くしてしまったもの。それは、此処では見つからないのだろうけれど。でも、もしも、もしかしたら――なんて、一縷の望みを抱いてしまう自分も居る。そう思うのはきっと、この海に伝わる伝承が、広がるあおいろが、あんまりにもやさしいものであったから。
導かれるがままにひかりを追い掛ければ、いつの間にそこにいたのだろう。いや、きっとずっとそばにいてくれたのだろう。色とりどりの小魚たちがラデュレの周りで戯れ合うようについてくることに気付いて、少女は微かに吐息を溢して咲った。
いのりのかたちはあれど、ねがいが叶うかはわからない。
でもきっと、それでもいい。
「(青い月に出逢えるのが、楽しみなのです)」
海の底で待つその御姿はどんな形であろうとも、ラデュレにひかりを見せてくれる筈だから。
第3章 ボス戦 『白月の幻主』

●きみにとどけ
瑠璃のみなそこに浮かぶ月が星を掻き消してくっきりとあおく浮かび上がっている。
ひかりの道を辿ったその果てに浮かぶこの姿こそが、伝承に伝わる『わだつみのブルー・ムーン』に違いないのだとその場に居た誰もが確信することが出来た。
天上のひかりを集めて青く輝くそのひかりに、ねえ、怖がらずに触れてみて。
あなたのねがいは、いのりは。ひととき、ほんのひとときだけ満ちるから。
たとえ一夜限りの奇跡であったとしても。
わだつみよ、月よ――どうか。
- - - - - - - - - -
第三章『白月の幻主』
彼の存在はこの海域では『わだつみのブルー・ムーン』と呼ばれ人々に御伽話の存在として親しまれています。
月に善悪の判断はありません。ただそこに在り、人々の想いを抱き。願いを叶えれば泡沫のゆめのように消えてしまうため、武器を構える必要はありません。
あなたの願いを、祈りを、ブルー・ムーンに届けること。
それがこの存在を正しく伝承通りの存在へと昇華させてくれることでしょう。
特別なねがいや、特定の『なにか』が無くとも大丈夫。
かわいい動物との触れ合いを望めば、あなたは大好きなふわふわたちと心ゆくまで遊ぶことが出来るでしょう。現実では起こり得ないような不思議なものを願えば、あなたはやわらかな雲に包まれながら虹色のキャンディ・レインを仰ぐことだって叶うでしょう。
もしもあなたが『あなたたち』であるならば、同じ景色を共有することもかないます。
もしもあなたが『もうこの世にいないひと』をのぞむならば、ブルー・ムーンは世界中を漂う|インビジブル《魂》からそのひとを連れてきてくれるでしょう。『この世界の何処かにいるひと』であるならば、微睡むゆめの中で暫しの再会を果たすことが叶うでしょう。(※参加者さん以外の他PCさんを描写することは出来ません、ご注意ください)
それがゆめか、うつつであるのか。
どのように受け取ることもあなたの心の赴くままに。
月のひかりはどこまでもあおく、やさしく皆さんを照らしています。
- - - - - - - - - -
●帰るべき■■
洗い上がった食器たちが水切り籠の中で水滴を光らせている。
ここは家だ。戀ヶ仲・くるり(Rolling days・h01025)が大好きな家族と過ごした、大切な場所。
「(なんだっけ?)」
すこしだけ靄がかかったような記憶を辿れば、そうだ。
「……寿お兄ちゃんが帰るから、好物作るんだ」
溢した言葉を耳聡く聞き付けたもうひとりの兄である祭が『え、俺の好物は?』とキッチンカウンターからひょこりと顔を出す。子どもみたいなその仕草に父も母も笑いながら『自分たちも』なんて次々言い出すものだから、キッチンに立つくるりはあっという間に揉みくちゃにされてしまう。
「ちょっとぉ! お父さんもお母さんも笑って乗らない! 収拾つかない!」
えー、とか。けち~! とか。甘えた非難の声なんてちっとも怖くないから笑ってしまって。
「もー! みんな大好きカレーに決定! 寿お兄ちゃんの好きなハンバーグ乗っけた豪華版!」
あたたかくて。やさしくて。当たり前にあった。
その筈、だった。
――ごめんなさい。
そんな甘ったるい朦朧とした景色を雨夜・氷月(壊月・h00493)はただひとつの観照体となってぼんやりと眺めていた。何にも脅かされぬ幸せな世界。絵に描いたような温かな家庭こそが、少女が求めて止まない元の世界に違いないのだろう。
触れたことのない景色にそっと手を伸ばし掛けて――やめた。
羨ましいのだろうか。いや、少しだけ違う。そこは少女の居場所であって氷月の居場所ではないのだから。触れてみたところでその温もりは自分には齎されず、ただ虚しさだけが残るのだろう。
「俺の居場所……」
願えば世界は紅く、蒼く自在に煌めいて。そんなきらきらとした世界が、ひとが、|愛おしく《呪わしく》て堪らない。
「……なんだっけ、それ」
面白いか、つまらないか。世界はそのふたつのみで構成されており、乾きを満たすためだけに彷徨うこの身にそんなものは果たしてあったのだろうか。
わからない。思い出せない。
そもそも必要であったのかさえ解せないことを、少し。ほんの少しだけ、気まぐれに、もどかしく思った。
「ぁ……、……氷月、さん」
薄れていく。消えていく。あまい余韻を残して胸を苛むじくじくとした痛みにくるりの瞳が揺れて滲む。
「おはよう、くるり。目覚めの気分はどう?」
「……泡みたいに消えちゃった、さびしい……」
氷月は常の調子を取り戻して笑い掛け、溢れそうになる涙を堪えながら言葉を痞えさせるくるりがなんとか言葉を紡ごうとするのを気長に待った。
「ごめ、……ごめんなさい、夢でも会いたかったのに」
帰りたい。でも、怖い。
いつかそれを認識出来なくなって、目の前に居ても会えないのだと思い知るのが怖くて、怖くて堪らない。
「んっふふ、何を言ってるのくるり」
認識することが出来なければ『帰った』ことにはならないだろうと。その不安さえ咀嚼するようにひとのかたちをした月が笑う。
「本当の意味で帰る為に俺に助けを求めたと思ったんだけど、違った?」
「私、」
どう、だったのだろうか。
いや――きっと。
堪えながら、嗚咽に声を詰まらせながら、それでもくるりは言葉を紡ぐ。
「はい。家族の顔を見て、声を聞いて、ただいまって言いたいです」
悪戯に拉致しただけではない。勿論驚く顔を見たかったのも本当だけれど、と氷月はにんまりと目を細めて少女の顔を覗き込む。
「コレはアンタが初心を忘れない為の投資」
これから何故くるりがそれを欠落するに至ったのか。その欠落の本質は何なのか。それらの謎を解き明かし、欠けたものを埋めていくこと。それこそが今日この月を探しに来た理由に他ならない。
「とんでもない|旅路《研究》の、第一歩だよ」
それは。自分は彼の|退屈《うつろ》を埋めるいい実験対象という意味なのではないだろうか。
けれど、それでもいい。それでもいいと思えた。
「……ちゃんと、終点まで付き合ってくださいね」
この旅のさいはてまで、懸命に生きて見せるから。
「勿論。成果を出してみせるよ」
少女の願いをその手に乗せて、うつくしき災厄は鷹揚に頷いた。
●最愛なる魔女へ
願いはみんなに幸福を齎すこと。それがアンジュ・ペティーユ(ないものねだり・h07189)を構築する魂の輪郭であり、彼女を空想した誰かの願いであったはず。
「とはいえ……その人の顔は知らないんだけどね」
どうか、どうかしあわせに。
己のさいわいでなく他者のそれに幸福を見出したひと。それがどんなひとなのかも分からないけれど、アンジュの胸にはいっとう輝く宝石のようないのりだけがあった。
このひかりさえあれば何処までも歩いていけると信じているし、今もその輝きは少しも色褪せてはいないけれど。もしもこの世界の何処かにそのひとのかけらがあるのなら、一目見てみたいとも思う。
「お願いしたら会えるかな……」
どこまでも澄んだあおいろに満ちた世界の只中で、アンジュはそっと瞼を閉じて朧げな願いのかたちを胸に描き出す。仰いだ月が言葉なき願いを受けて、柔く。包み込むようにアンジュを照らし出していく。
「(あたしを空想した誰かに会わせて下さい)」
ひかりが、触れる。アンジュはその時、かたちなきインビジブルたちが瞳の奥で確かに揺らめくのを感じていた。
――なにを描いているの?
――魔女だよ! みんなのゆめを、ねがいを叶える魔女なんだ。
――そう。それはとっても素敵だね――。
世界が割れる。
音を立てて崩落する景色の中で、思い出だけが鮮烈に輝いていた。
■■はきっともうこの世界のどこにもいない。それでも――■■はわらっていた。その瞳になないろのひかりを宿して、嘗てちいさな手で描いたのであろう|魔女《アンジュ》を、宝物のように胸に抱いて。
これは誰かの記憶。いつか何処かで描かれた、はじまりのものがたり。
「……ブルー・ムーン、ありがとう」
ひかりに紛れその顔を判別することは出来なかったけれど、砂となって消えゆくいとしいゆめは、確かにアンジュと喪われた魂を巡り合わせてくれたのだ。
名前も顔もわからない、いつか何処かで生きていた、あなた。
あたしを思い描いてくれてありがとう。
あなたのお陰で、毎日が楽しいよ。
●いつか見た願いのかたち
「願い、祈りを届けろ――か」
それは多くの錬金術師に、否、叡智の探究者たちにとって。果ての見えぬ探究の旅路の先にあるものであり、時に縋るような想いで手を伸ばす行為なのだろうと、ウィルフェベナ・アストリッド(奇才の錬金術師・h04809)は己が歩んできた学びの路を思い浮かべながらちいさく呟く。
「他√であれば机上の空論とも云える代物を実現させてしまえるのが、錬金術だろう」
それ故にウィルフェベナは理想ではなく現実を視る。夢という朧げで不確実なものには是を唱えず、探究の末に解明することの叶う学術に重きを置くと云うのは彼女の見解ではあるけれど。
「……まぁ、そのせいかバカ弟子は現実主義に更に拍車をかけてしまっているが」
「いや、なんでそこで俺?」
育て方を間違えたろうか、なんて。やれやれと殊更に呆れたように肩を竦めるものだから、それまで言われるままであった千堂・奏眞(千変万化の錬金銃士・h00700)は実に不本意であると眉を顰めながら師を仰ぐ。
「願いや祈りなぁ……ホント、オレには無縁だと思うんだけど」
「何故、お前さんは夢を見ようとしないんだ。人生を損しているぞ、全く……」
「何でって…………師匠ならわかるだろ?」
自分は心や感情の機微に絡んだものには疎いのだと。
なんて事のないことのように語る奏眞に現実を説いたのは自分だ。それでも、理念はあれど愛弟子である少年や共に歩く少女が未来に夢や希望を抱いて瞳を輝かす様が尊くないわけがない。そんな世界へと先達である自分が導いてやろうという気概は勿論あるが、如何せん彼女もまた少しばかり不器用で、『ひと』と云う最も壮大な表題に取り組んでいる最中であった。
「(……願わくば、奏眞が少しでも穏やかに在れる日々が訪れればいい)」
そう願うことくらいは。きっと、この青い月も許してくれる筈だから。
「(願いや祈り……。あたしはやっぱり、誰かに会うとかは望みたくないって思っちゃうな……)」
もしもこの世界の何処かに居るひとであるならば、自分の足で会いに行きたい。
もう二度と会うことが叶わないひとであるならば、思い出の中に大切に仕舞っておきたい。
己が胸にてのひらを当てて目を伏せた霧谷・レイ(自称 「神秘の美少女錬金騎士」・h03818)は、浮かぶ月のひかりが瞼を通してあおく煌めいているのを確かに感じていた。
「レイもお願いをしてきたらどうだ?」
声にはっと顔を上げれば、こちらの様子を気遣うような奏眞と視線が重なって。にこりと何時も通りの笑顔を浮かべたレイは『うん』と頷き月をのぞむ。
「夢を見るならそう、スケールでっかくて楽しいものを見たいよね!」
ぱちん、と。あぶくが弾けるような音がレイの声と重なったかと思えば視界は一転して三人は『ほんとうの星の海』へと放り出され、慌てて手足をばたつかせて見れば先とは違って正しく重力を失った世界で星々の合間を揺蕩うひかりと共に泳ぐことが叶った。
「う、浮いてる!?」
「あははっ! ほらね、こんなふうに宇宙旅行とか!」
「ふむ、レイはまた壮大な願いだな」
いつか地上の戦いがなくなって。人々が宇宙に触れられるようになって。たくさんの星々を旅したら、どんな出会いが待っているだろう。ことばが通じる子たちはいるのかな。争いがなくなったなら、仲良くなることはできるかな?
少女の描いた|未来《もしも》は純粋で、あんまりにもまっすぐで。奏眞には少し眩しいくらいで思わず言葉を噤んでしまう。
「バカ弟子も少しは見習え。夢を見るというのは、こういうものなのだぞ」
「千堂くんも、何も思いつかないならなんか面白いこと考えればいいんじゃ……」
ウィルフェベナも、レイも。奏眞のやさしさを知っているし、だからこそ彼にも束の間の夢を見ることくらい望んでもいいのではないかと口にするけれど。少年は緩やかにかぶりを振って、『ふたりの願いが叶えばいいさ』と困ったように微笑んだ。
「オレは、いいんだ。……そろそろ地上に戻ろうぜ、宇宙旅行も良いけどさ」
「あ……いや、そうだね! そろそろ帰ろっか!」
ひかりの道を、きた道を辿って。星の海からうつつの海へと再び泳ぎ出していく。
あおい月が遠ざかる。ひかりが、天のものへと移り変わっていく。
『――――っ』
「……ん?」
「千堂くん?」
不意に、誰かに呼ばれた気がして振り返る。
けれどそこには誰の姿も見当たらず、気配さえ感じられない。――当然だ。自分は何も願うことなく、月から背を背けたのだから。
「いや、何でもない。気のせいだったみたいだ」
こちらを伺う精霊たちやレイに笑み掛け、少年は再び水を蹴ってみなもへと向かっていく。
月あかりのその先に立っていた幼い子どもの輪郭は奏眞が無意識に祈り願った想いの残滓。朧げなその姿は祈りの主に言葉をかけないまま。いつまでも、いつまでも。うつしよへと向かう奏眞の背を真っ直ぐに見詰めていた。
●マシマロ・フラッフィ
「これが、ブルー・ムーン?」
くれないの瞳にあおいろのひかりを落としながらララ・キルシュネーテ(白虹迦楼羅・h00189)が紡げば、どこか惚けたように月を見上げていたセレネ・デルフィ(泡沫の空・h03434)は縋るようにちいさな迦楼羅の手を握り直した。
月はそこに在る。そこに在るのに、己が求めるそらの月ではない。
この月を『善きもの』のままにするならば――彼女とふたりでそうするならば。
「……私は、ララさんと共に、幸せな世界を楽しみたいです」
願えばきっと月はララとセレネが見たいものを見せてくれるのだろう。けれどやわらかなひかりが齎すものは、やさしいものであったとしてもその儚さが故に残酷でもある。それは泡沫の夢に他ならず、手を伸ばしても届かないのだと思い知ってしまうから。だから。
「ララも胡蝶の夢よりも、お前との今を楽しむものがいいわ」
怖がるようなセレネを仰げば、呼吸の仕方を漸く思い出したかのように少女がはっと息を吸うのに、幼き雛は三日月のように瞳を撓め微笑み掛ける。
「セレネはもふもふしたものは好き?」
「もふもふ……! すきです、とても。埋もれたいくらい……わ!」
口にし終えるよりも僅かに早く、ぽん、ぽぽん、と綿の実が弾けるような軽い音と共にふたりの周りに動物たちが飛び出してくる。おひさまをいっぱい浴びた小麦色のうさぎに、綿あめみたいにまっしろな猫。雲のようにぼふぼふとした毛並みの犬はセレネの背丈よりもおおきく、それよりさらに巨大なひよこがふたりを背に乗せるように現れたものだから、セレネとララはあっという間に押し寄せてきた毛の塊に埋もれてしまった。
「ララさん、みてください……! あっちに猫さん……うさぎさんも、犬さんもいます……!」
「この子はひよこね。見て、ララ埋もれてしまったわ」
ぎゅっと抱きしめてみればそれらは確かにそこにいて、やわらかな毛並みといきものの温もりを伝えてきてくれる。あたりの景色はいつの間にかあたたかな日差しが落ちる草原へとすがたかたちを変えていて、それはきっとふたりが互いに想う温度の表れなのだろう。
「セレネも一緒にもふりましょ?」
「私もさわらせてくれるでしょうか……」
瞳をきらきらと輝かせながら覗き込んでくる動物たちにはただ真っ直ぐな親愛があって、その純粋な好意がセレネの緊張を解いてくれる。
「……! ふかふか、もふもふ……!」
恐る恐るに手を触れさせれば、どこまでも手が沈んでいくことに驚いて慌ててララを仰ぐから、『大丈夫よ』と咲えば安堵したセレネもほわりと柔く綻んだ。
ふたりを乗せたおおきなひまわりいろがふわふわと宙に浮かんでいる。
ひよこが宙を飛ぶなんて、なるほど確かに泡沫のゆめに相応しい。寛ぐ動物たちを存分に撫でつつそらを游ぐ中、ふと。悪戯を思いついたかのように目を細めたララがそっとセレネの翼に触れる。
「どの子も素敵なもふもふだけれど。一番は……お前の翼かしら?」
「ひゃう……!? び、びっくりしました……」
そらに焦がれたうつくしき白。穢れなきそのいろが、どんなにやさしいかをララは知っている。雪のようにしろく、絹のように滑らかな感触を慈しむように撫でれば、セレネの頬がぱっとあかねいろに染まる。
「そんな、ララさんの……尻尾とか、翼の方が、素敵です」
「ララのも素敵? 嬉しいわ」
ぱちりと瞬いた紅の花が、間近に見えるそのいろが、やっぱり綺麗で。とても、きれいで。
「……その、触れても、良いですか……?」
きっとそのねがいは伝承の月にだって叶えることなんか出来やしない。懸命に勇気を振り絞って伝えてくれたのであろう唯一ののぞみを叶えられるのはララひとり。もちろんと頷けば、花咲くように微笑ったセレネのてのひらが可惜夜に触れるのに、擽ったそうに翼を震わせたララは甘えるようにセレネの肩へと身を寄せる。
「やっぱり……綺麗で、すてき」
「むふふ。やっぱり夢より、現がすきよ」
こうして触れて、分かち合うことが出来るからと。少女たちは密やかに笑みを交わし合った。
●惑星系003より
ただ静かにそこに在って、願いを叶えてくれるお月さま。
自分もそんな風になれたらなんて、すこしの親近感を覚えながら月夜見・洸惺(北極星・h00065)が月を仰げば、あこがれを口にするよりも早く元気いっぱいに諸手を挙げる集真藍・命璃(生命の理・h04610)の声が重なって、思わずふっと笑ってしまう。
「はいはーい! 命璃ちゃんは世界中のふわもふに囲まれたいですっ!」
「僕は宇宙の天体に触れてみたいなぁ……、……わわ、惑星が落ちてきた?!」
それは子どもが一生懸命描いた宇宙空間のような、甘くてきらきらして眩しい、真昼のゆめのような景色であった。ぴかぴかと明滅しながら降ってくる彗星に洸惺は慌てて命璃を守ろうと身を翻すけれど、ぶつかったそれは気の抜ける感触と共に紙風船が破裂するように呆気なく砕け散ってしまった。星の残滓を全身に受けながら振り向けば、少年少女のはしゃいだ声がクレヨンの宇宙空間に満ち満ちる。
「凄い、凄いっ! 本当に宇宙にいるみたいっ」
「洸惺くん見て見て! あっちにはもっこもこのふわっふわ!」
ずっとずっと憧れていた。
あたたかな家の中でふわふわの動物を抱いて過ごせたら、どんなにしあわせだろうかと。
星の間を行進するように動物たちがずんずんと宙を歩いている。星座を結んだら彼らが生まれたのであろうか、命璃たちを見つけた大小さまざまなもこもこたちは遊んでくれる存在を発見したとばかりに駆け寄ってくるものだから、命璃を乗せた洸惺は驚いて飛び上がってしまう。
「あっ、人に化けたらダメだよ?」
「……え、人に戻っちゃダメなの?」
この脚では彼らを抱き留めることができないよ、なんて。小首を傾げる洸惺の背をぎゅっと抱いて命璃は笑う。
「洸惺くんも命璃ちゃんのふわもふ軍団の立派な一員ですから!」
おひさまみたいに眩しく笑う彼女の無邪気さに根負けするように、洸惺もくすくすと声を立てて笑えば追い付いてきた動物たちをその背に招くように身を低くする。
「じゃあこのまま宇宙を翔けちゃおうかなぁ」
おおきな動物さんたちは一緒に。ちいさな子たちは背中の上で。きらめく星々を八つの脚で蹴りながら、洸惺は高く、より高くへと身を躍らせた。
「あ、恐竜さんも!」
獣脚類と呼ばれる肉食恐竜たちの中には、被毛を持つ存在がいたのかもしれない――とは、近年の研究で証明されつつある仮説のひとつであった。この宇宙では命璃と洸惺の『もしも』を忠実に再現しているのであろう、洸惺の体躯をゆうに越す恐竜が膚を震わすほどの大きな挨拶するのに声を上げれば、命璃はころころと可笑しげに声を立てた。
「凄い、僕よりも大きい!」
「ね、カカポとキーウィも居るねぇ!」
絵に描いたようなまるい輪郭のみどりとちゃいろ。翼はあるが何故か空を飛ぶのが苦手で、人懐っこすぎるが故に数が少ない。なんだか愛嬌のある彼らの名前を口にすれば、洸惺は宙をふよふよ漂うそれらを脅かさないようにそっと歩み寄る。
「カカポさんとキーウィさん、初めてみたよ!」
「洸惺くんっ。ほら抱っこしてみよ?」
飛べない翼を羽ばたかせるけれど、抱き上げればすぐに大人しくなる。こんなに警戒心が無くてどうやって生きてきたのだろうかなんて疑問が浮かんできそうなものだけれど、
「ほんっとにキュート!」
「ねえ、抱っこって言いながら僕の背中に積まないで!?」
犬やら猫やら鳥やらで洸惺の背中は大渋滞。そんな様子はお構いなしに命璃はひらりと星の上へと飛び降りる。彼女の視線の先には彗星と一緒にころころ転がっていくアザラシが居るのだけれど、置いていかれた洸惺の背の上では動物たちがわんわんにゃあにゃあ、大合唱が止まらない。
「待って、僕の背中の子たちはどうするの……!?」
ちいさな抗議なんて聞こえないふり。
洸惺が自分にかなわないことなんて、命璃にははじめからお見通しだから。
「んふふ、さいこーだねぇ」
一夜限りのゆめだなんて惜しくなってしまいそうだなんて。命璃は捕まえたアザラシの赤ん坊をぎゅっと抱きしめ、ふわふわの毛並みに頬を擦り寄せた。
●遠雷は降り注ぐ
あおく満ちて、澄んで。しじまの海に月が浮かんでいる。
月の光は見上げるものではあっても、祈りや願いを乞う存在だと認識したことはなかった。
「へぇ、此れが『わだつみのブルー・ムーン』」
地上の月と星のひかりを集めて輝きを放つそれは、成る程確かに御伽話の中のような存在だと。緇・カナト(hellhound・h02325)が眩しそうに目を細めるのに、トゥルエノ・トニトルス (coup de foudre・h06535)は『そうだろうそうだろう』とまるで我が事のように喜び勇んで頷いた。
「海月と呼ばれる生き物もいるようだが、空浮かぶような月はやはり規模も違って……吸い込まれるような美しさだ!」
何でオマエが喜ぶんだよと軽く小突くカナトの所作など軽いもの。主とこの景色を共有出来たことが嬉しいのだと、幾度か重ねた言葉を今一度口にすれば不器用な黒妖犬はそろりと主から視線を外す。
「さて、主の叶えたい願い事は?」
なんて。彼が独りで全てをこなそうとする存在であることくらい出会った当初から知っている。だから、トゥルエノには次にカナトが何を口にするかと云うことだって大体見当がついていた。
「……確かに、逢おうと想っているヒト達はいるとも」
それは夢想ではなく現実で。独りで成そうとしている事だから。
「此処で乞うような願いでは、ないな」
「だろうなぁ」
答えを口にすることを躊躇っていた。腹の中ではじめから決まっていたのだろうにそうしなかったのは、『夢がない』なんて言われてしまうことが面倒だったからだろうか。いや――トゥルエノがそんなことを言うような|ひと《精霊》ではないことくらい、カナトにだってとっくの昔に分かっているのだけれど。
「我はキミに幸い多く在るようにと祈ってもいる!」
堂々と告げるその言葉に迷いはない。尤も、これは常日頃から思っていることであり月に懸ける願いかと言えば否である。そうしてみればどうしたものか、ほんとうに『この景色を共有すること』だけが願いになってしまったと。可笑しげに笑うトゥルエノの姿にカナトは片眉を上げて目を瞠った。
「トゥルエノの願いを届けても良いだろうに。まぁ欲の無い精霊様なことで」
呆れたような言葉に少しの照れを滲ませる。彼の言葉は良くも悪くも真っ直ぐ過ぎて、真正面から受け止めるには少しばかりの面映さがあったからつい皮肉を口にしてしまうけれど。トゥルエノは然して気にした風もなく、ただ表面上の茶化すような言葉に唇を尖らせて見せるだけだった。
「むう。事実なのだから仕方ないであろう!」
「……それじゃあ、オマエの住処の光景でも望んでみるか」
いつか共に見た夕暮れを海底で願うのも奇妙な話だけれど、と。肩を竦めて笑うカナトの横顔を鮮烈なる霹靂が青く照らす。曇天の空に響き渡る雷を反射して、鏡面の湖が幾重にもひかりを反射していた。トゥルエノにとって最も馴染み深いその光景が一面に塗り替えられて広がっていくのに、少年のかたちをした雷獣は頬に喜色を浮かべながらカナトを見上げる。
「主がこの場所を気に入っているのであれば、精霊側としても誇らしいぞ……!」
雷は生命にとって畏怖すべきもの。畏れられることはあれど好まれることは余りないからこそ、カナトがそれを願ってくれたことが嬉しくて。晴れぬそらに迸る閃光を仰ぎ、トゥルエノは軽やかにカナトの手を引いて走り出す。
「……っ、オイ!」
「曇天の先にあるものも、また晴れやかなのは事実だしな!」
天に躍れ。地を駆けよ。
その先にある未知が、よろこびであるものと信じて。
子どものように燥ぐちいさな手に導かれながら、カナトは緩やかに吐息を溢す。
「ここまで連れてきてくれて有難うな」
「ふふ。幾らでも何処へでも連れ出してみせよう」
夜明けまでと言わず、何時までも、何処までも。
共に歩んだその先には、未だ見ぬ驚きとさいわいがきっと満ちているから。
●刹那のアンバー
ひかりのいろが白から青へ変わったのは、一体いつからだったのだろう。足を進めたその先に映る懐かしい色彩に、懐音・るい(明葬筺・h07383)はぱちりと一度大きく瞬いた。
今はもういない。兄のように慕っていたひと。もう二度と会うことは叶わないと思っていた、大切な。
「(私にとって だいじな人)」
榛のいろが、髪が、緩やかにこちらを振り返って。ブラウンの瞳が驚いたように見開かれ、すぐにやわらかく細まって。仕方がないとでも言いたげに呆れた吐息を溢すものだから、るいの鼓動は微かに早まり、呼吸をすることさえ忘れてしまったことに気付くのは随分あとになってからだった。
その姿が本物であるのか、或いは自分の願いが生み出した幻想であるのか。物言わぬ月は何も答えてくれないけれど、どちらでもよかった。彼はただそこに居て、置き去りにした日々の延長線のように優しく名前を呼びながらるいの言葉を待ってくれている。
「ぁ……」
言いたいことも思っていたことも沢山あった筈なのに、上手く言葉が紡げない。
懊悩のなかにひとつ。たったひとつだけ、彼に直接伝えたかった言葉があった。それでもそれは音にならず、ついには直接伝えられることのないまま――それがずっと胸の中で燻り続けていた。理由なんて『何となく、気恥ずかしかったから』とか。改まって口にするのもなんだか照れ臭く感じてしまって、今更言うほどのことでもなかったと思っていたらその言葉はとうとう永遠に伝える機会を失ってしまっていた。
「――――、」
息を吸って、吐いて。
なんてことのないその言葉を、大切に、慈しむように口にする。
「ありがとう」
わたしのたいせつな人。
音にすれば呆気なくて、それでも網膜に薄く掛かった靄が晴れていくような心地がして。セピアの面影が記憶のままに綻ぶのを、るいは何時までも眩しそうに見詰めていた。
●『かみさま』
いつか、夢で出逢ったあの子に逢いたい。
今の自分はあの子の顔も、名前さえも思い出せないけれど。
「(ブルー・ムーンはそれでも叶えてくれるかしら)」
揺らぐ海水にリラの甘やかな髪を遊ばせ、シルフィカ・フィリアーヌ(夜明けのミルフィオリ・h01194)は祈るように、願いを込めてやさしいひかりにそっと手を伸ばす。ほんの僅かに月の輪郭がぶれて、ぱちりと目を瞬かせたその先に広がっていたのはペンタスの花畑だった。
はじめて見る筈なのに、何故だろう、涙が出そうなほどにいとおしくて懐かしいのは。
黎明のいろを宿した花々の中心に誰かが立っている。後ろ姿が、ゆっくり。ぱらぱらとフィルムを捲るように、ゆっくりと振り返って――息を呑んだのは、きっと同時だった。
『――シルフィカ?』
その姿は想像よりもずっと大人びていたけれど、直ぐにそれが『あの子』であるとシルフィカには直ぐに分かった。目をまん丸く見開いたかと思えば次にはくしゃくしゃと泣き出しそうに顔を歪めて、何度も名前を呼ぶその声は幼子のように震えていた。
「大丈夫よ」
今のシルフィカにひとの子の名を呼ぶことは出来ないけれど、手を伸ばせば容易く抱き締めることが叶う。涙を伝ってその温みが消えて仕舞わないようにと背を摩れば、それよりも何倍も強い力でひとの子はシルフィカの身体を抱き返す。
『シルフィカ……シルフィカ!』
「……ひとの身である今なら、こうやって抱き締めることも出来るのね」
あいたかった。逢いたかった。
他の何もいらない。ただあなたにあいたかったと。子どものように泣きじゃくるその背中を、シルフィカは柔く、優しく抱き締め続けた。
瞬きほどのゆめだった。
目の前にはただ優しいあおいろだけが広がっていて、静寂が身体だけを置き去りにしているようだった。それでも――シルフィカの腕には涙の跡とぬくもりが確かに残っている。
「(そう、あなたは今も……この世界の何処かにいるのね)」
星の破片はこの胸の中に。
願いを乗せた花の香りが、頬を微かに撫でた気がした。
●いつか、戦いの終わりに
願いは決めていた。でも、『そのもの』ではない。
祈るように。縋るように。叫び出したいほどの衝動を乗せて、クラウス・イーザリー(希望を忘れた兵士・h05015)はそっと月のひかりに手を伸ばす。
映るはまぼろし。
望めばきっと、月は善悪の是非もなく彼そのものを連れて来てくれただろう。けれど、そうしなかった。
「……幻ですらこれなんだ」
歓喜。後悔。幸福。悔恨。
あらゆる感情が同時に湧き上がり、まるで生きたままはらわたを引き裂かれるかのように胸の中が掻き乱されて視界が揺らぐ。本物の彼を願ってしまえば。彼とまた逢えたら。もし、そんなことが叶ってしまったら、自分がどうなってしまうかわからない。
心なき兵士であれば、戦いに身を投じてさえいれば己を殺せた。懺悔も義憤もすべてすべて、撃鉄と弾丸に乗せてしまえばそれでよかった。それなのに、自分がひとであることを思い出してしまったら。生きる理由に疑念を抱いてしまったら。もしも彼自身の魂を願ってしまえば、自分はきっと如何にかして彼を現世に留めようとしてしまう。或いは――夜明けと共に再び消えてしまう彼に、『共に連れて逝ってくれ』と願ってしまう。
「それはきっと、……良い事じゃないから」
苦く噛み殺すような笑みに、■■■■■のすがたかたちをしたまぼろしはやわらかく微笑み返す。くしゃりと子どもみたいに笑うその姿は生前の彼の面影と瓜二つで、思わず嗚咽が溢れそうになるのをクラウスは咳き込むことでなんとかやり過ごす。
最期の記憶を少しだけ。ほんの少しだけ和らげてくれるそのまぼろしは、ただ、静かで優しかった。
――このまま時が止まってしまえばいいのにな。
まぼろしは何も語らない。けれど、それでよかった。
あおき世界のさいはてで、ふたりの戦士の影は寄り添いながらその景色を目に焼き付けるように静かに眺めていた。
●五月雨
別れは至極唐突に訪れ、世界は当たり前のようにその事実だけを粛々と受け止めた。
春風に乗って仄かに花の香が漂う頃。中学三年生だった水無瀬・祈(五月雨・h06808)は両親と共に一族総出の観桜会に向かう筈だったけれど、祈だけが偶々風邪を拗らせひとり自宅で臥せっていた。翌朝熱が引いても帰らぬ両親を心配していた祈の耳に届いたのは、言葉にすれば余りにも呆気ない、水無瀬の一族と両親の訃報であった。
突如襲った怪異と水無瀬の一族の死闘は夜通し続いたのだと云う。
折れた刀と貌さえ判別出来ない遺体たちが棺の中に無理矢理押し込まれているのを、何処か他人事のように見詰めていた。汎神解剖機関が執り行ってくれた一族の合同葬儀の最中、祈はただ沢山並んだ遺影の中で呆然と立ち尽くすばかりで、きちんとした別れさえ言うことが出来ないまま彼等が灰になっていくのを黙って見詰めていることしか出来なかった。
会いたいなんて、弱い。
逢いたいなんて、未熟だ。
「それでも……会えるなら会いてぇよ」
引き返そうと何度も己を律した。憂いも迷いも己が青さを浮き彫りにするばかりで、守る者たらんとするならば捨てなければならぬ感情だと、何度も、何度も言い聞かせた。
でも――『信じて』と。他ならぬ彼女が言ってくれた。
泣き腫らした目を擦ることも忘れたまま訴えられた彼女の願いを、祈りを、無駄にはしたくない。だから。
「父さん、母さん……」
ひかりに、触れる。
その瞬間に五月の陽だまりが、懐かしい藺草の匂いが、風と共に広がっていくのを祈は確かに感じた。
稽古の時は鬼のように厳しくて、それでも絶対に突き放すことはしなかった父。清貧を心掛けた暮らしの中でも心を豊かにする工夫をするのが得意で、いつも家族を一番に気に掛けてくれた母。
真新しい記憶の中で無惨なあかいろを晒していた面影はそこには無く、思い出の最奥に大切に仕舞い込んだそのままの姿で目の前に立つふたりの姿に、浅葱の双眸から滂沱の如く雫が溢れることを止められなかった。
「父さ……、……かあ、さん」
俺も一緒に行きたかった。
二人と一族の皆の役に立ちたかった。
「俺なんか……、生き残っちまって、ごめ……、ごめんな」
手が、当たり前のように伸びてくる。
『背が伸びたな』と目を細める父。『ずっと見ていた』と、母が微笑む。
頭に乗せられた、涙を拭う、剣ダコのある硬いてのひら。もうずっと忘れていたその感触に嗚咽を溢せば、『しゃんとなさい』なんて。そんな風に窘められることは、もう、二度とないと思っていた。
「……俺さ、新しい家族が出来たんだ」
いつか二人が決めたひとと当たり前のように見合いをして、当たり前のように結婚するんだと思っていた。だけど、生まれてはじめて好きな人ができた。何より大切にしたいものが、たくさん、たくさんできた。
自分は未熟で弱くて、独りじゃ何も出来ないけれど、支えてくれる人がいる。だから、転んでも、泥を啜っても、生きてやろうと思える。思えた。だから。
「頑張って二人みたいに強くなるよ」
――だから今だけ。前みたいに、
「祈って、よんで」
顔を見合わせたふたりの顔が、くしゃりと笑う。いつも難しい顔をしている父が時々そうして子どもみたいに笑うのが、まるで認められたような気がして祈はいっとう好きだった。
『祈』
そうして母が困ったように眉を下げて笑うのが。子ども心に赦されたような気がして、祈はこっそり甘えていたことを今更ながらに思い出す。
『生きなさい、祈』
視線が重なる。
涙に濡れたその先に、指し示した陽が巡るのを。最後の水無瀬を背負った少年は、迷いを捨てた目で確りと見た。
『魔を祓ったその先で――必ず、雨は上がるのだから』
●夢見草
「わー! 綺麗な月だ!」
ブルー・ムーン。ほんとうのほんとうにいたんだとエオストレ・イースター(桜のソワレ・h00475)が瞳を輝かせながら歩み寄れば、不意に。ざあ、とひかりの粒が一斉に舞い上がるものだから、思わず『うっぷ!』と顔を守ってしまう。
星のひかりではなかった。
宵の空を背に舞い散る桜の花弁が輝いている。ぼんやりとした月の輪郭に触れ、きんいろの花が舞っているかのようにさえ思えて。やわらかな香りと花吹雪に咲樂・祝光(曙光・h07945)が目を瞠らせば、足元に軽い感触がするものだから。視線を下せばそこには愛らしい迦楼羅の雛が確かに在って、懐かしい声で『にぃに』と甘えた声で己を呼ぶものだから、思わず息を詰まらせてしまう。
「(――あ、ここは……祝光の家だ!)」
何度も遊びに行った懐かしい友の家。がらりとそのいろを変えた世界を見渡せば、エオストレはそれが祝光の願いを反映した夢であることを知る。
『兄様』
鈴を転がすような声に振り向けば、辺りを舞う花弁と同じ彩を宵の穹に流す娘がしずしずと歩み寄ってくる姿が見えて。ふたりの妹たちに手を引かれながら、祝光はあの日そうしてきたままに母屋へと続く路を歩む。屋敷の扉を潜ればそこには当たり前のように、天の乙女が如きうつくしき母が『お帰りなさい』と出迎えてくれる。
「(祝光の妹達に、お母さんとお父さん)」
種こそ違えども、そこに在るのは穏やかな温もりに包まれた家族の姿。桜の花弁と共に漂いながらその光景を目にしていたエオストレの胸には、友を想うあたたかな気持ちとほんの少しの寂しさがあった。
『お前が龍王になるとはな』
祝光と父は常に衝突してばかりだった。偉大なる迦楼羅天たる彼が笑っている姿を見たのは、もう随分遠い記憶のような気がして。ああ、自分は確かに家族に誇れるような龍王と成れたのだと――やわらかな家族の面影だけを胸に残して、やがて光は消えていく。
「夢、」
桜に攫われたような心地がした。
ひかりのしるべだけを残してさらさらとその姿を消していくあおい月を見上げ、未だ醒めやらぬゆめの中に心を置き去りにしたままの祝光へ、エオストレは僅かな苦みを笑みに乗せながら穏やかにその名を呼んだ。
「君は、龍王になりたいんだ」
家族のために。だからこそ、幼い頃から修行の旅に励み懸命に今を生きているのだと、今なら分かる。
「――……そうだったんだ」
「……君には知られたくなかったな」
|神鳥《ガルーダ》の因子を強く持つ己の身。自分は龍であるはずなのに、その見目のすべては受け継がなかった。けれど、それでも幼き日に抱いた誓いを捨ててはいない。
「色々あるんだよ」
彼が持つはずであった神刀は今、エオストレの手の中にある。彼が溢した短い言葉にどれほどの想いを詰め込んでいるのだろうと思えばそれがなんだか酷く申し訳なくて、しゅんと長耳を垂らした友の姿を見れば祝光はそっとその肩に手を置き微笑み掛ける。
「俺はきっと叶えるよ」
虚勢ではない。そこには揺らがぬ決意と信念があった。
今は未だ路の途中だったとしても、きっと。いつか、必ず認めさせてみせるからと。その瞳に宿る意思のひかりを真っ直ぐに見たエオストレは、今度こそ心の底からの笑みを向けて友を仰ぐ。
「ん、祝光ならなれる! 僕も応援してるし、いつだってイースターは君の味方!」
俯く子らには手を差し伸べよう。涙を流す子らには奇跡を見せよう。皆に陽だまりのような笑顔を――それこそが春を齎す|厄災《祝祭》の本懐であって、それが身近な存在であるならば尚のことに違いない。
「……君に励まされるのはなんだか妙な心地だ」
それってどういう意味さ! なんて。ぷうと頬っぺたを膨らませて抗議するエオストレにも、それをあしらう祝光にも。もう、憂いの色は少しも残っていなかった。
●虹をかけて
「わだつみの、ぶるー、むーん」
御伽話とは誰かが見たゆめのかたち。こういうものを『しんぴてき』という言葉を使う景色なのかな、なんて。継歌・うつろ(継ぎ接ぎの言の葉・h07609)は無垢なる瞳を瞬かせながらあおく輝くみなそこの月を見上げていた。
「願いを叶える月か……」
今此処に居ない者と再び巡り逢わせてくれるのならば、道を違えた友とも再会を果たせるのだろうかと――思い掛けて、否、と神花・天藍(徒恋・h07001)は緩やかにかぶりを振って浮かび掛けた願いを胸の中に閉じ込める。
「(彼奴と道を違えたのは己が責)」
例え虚構の存在であろうとそれに縋ろうとするなど、都合がいいにも程がある。自嘲に目を伏せ掛けた天藍の袖を微かに引く感触に意識を向ければ、そこにはもじもじと落ち着かない様子のうつろの姿があって。
「天藍さん、天藍さん」
「ん? 何だ?」
言おうか言うまいか。己ののぞみを口にするのを迷う少女を促せば、それをゆるしと理解したうつろは気恥ずかしげに頬を染めながら恐る恐るに口を開いた。
「耳、かして? あのね、あのね……」
紡がれるは他愛無い、けれど純粋がゆえに澱みのない愛らしいゆめの輪郭。
「空の上の遊園地で遊びたい?」
「うん……!」
ものをねだることが不得手であろう少女が齎した可愛らしい夢を、どうして無碍に出来ようか。『ゆうえんち』なるものは天藍には馴染みの薄い言葉ではあったけれど、それを月に託すのならばふたりで願おうと。やわらかく齎された肯定に、うつろはきらきらと瞳に星を宿しながら何度も頷くのだった。
もくもくと月が一生懸命湧かせた雲はあっという間にふたりを包んで、浮かんだ先からがらりと景色は変わっていく。青空にかかる虹の橋の上では風船を持ったおおきなぬいぐるみたちが滑り台のように弧を描くなないろのひかりの上を滑っていて、パステルカラーの遊具達はまるでキャンディ・ポットをひっくり返したかのよう。
ここは空の上の遊園地。おなかに雲を詰めたふわふわのぬいぐるみたちが作ったゆめのおしろ。
「わわっ、わあ……っ!」
ぎゅっとわたあめを押し固めたような雲の上でぴょんと跳ねれば軽く弾んで。燥ぐ声を上げるうつろの横で、はあ、とか、ほお、とか、少女の描いたゆめのかたちに驚くばかりの天藍が感嘆の声を上げるのが何処かちぐはぐで、それがまたおかしくて少女の笑顔を優しく誘った。
「天藍さん、見て……! ひこうきが、ブーンって……あれも、あとらくしょん?」
「あとらくしょん……なるほど、あれらが遊具なのだな。あれも楽しそうではないか」
手本を見せてくれているのか、虹の橋を滑り降りるぬいぐるみたちを指し示せばうつろの頬は歓喜のいろに彩られた。
「わたしも、乗りたい……!」
遊び方が分からなくても彼らが楽しみ方を教えてくれる。おもちゃの飛行機をそのまま大きくしたかのような遊具にふたり乗り込めば、ぽこぽことあまい煙を出しながら緩やかにそらを走り出すものだから。あっという間に雲が遠くなっていくことが楽しくて、少女と冬の花は何処か夢心地で広がる景色を天から仰いだ。
「もっと、もーっと、高い所のけしき、見られるね……!」
「ああ、そうだな」
有り得ぬとしてもこれはゆめ。彼女が描いた憧憬なのだと思えば中々に楽しいと天藍は少女の横顔を眩しげに見詰め――その視線に気付いたうつろは少しだけ照れたようにはにかんで。
「あ、あの……おねがいごと、付き合わせて……、」
こんな時まで謝罪のことばをのぼらせる。それは彼女の美徳ではあるけれど、今宵くらいはずっと咲っていてほしいから。天藍はその先を言うのは無粋だと、しい、と己が唇に指を立てて見せる。
「いや、構わぬよ。我も楽しかった」
むしろ、助かった――そんな言葉は心の裡に仕舞い込んで。
うつろのかんばせがほにゃりと綻ぶのを見て、天藍もまた柔らかく微笑んだ。
●そらが白むまで
「……これが、ブルー・ムーン」
月は静かに佇んでいて、地上のひかりをすべて吸い込んだかのようにあおく、あおく澄んでいる。綺麗だな、と少しだけそのひかりを惚けたように見詰めていた祭那・ラムネ(アフター・ザ・レイン・h06527)は、ここまでやってきた祈りのかたちを青い月へと掲げるために大切に下げていた胸元の輝石を掬い上げた。
「俺さ、不眠症で」
くすりをたくさん飲んで無理矢理に眠ろうとしても眠れない。それでいてからだは頑丈すぎるくらいで体力もあるものだから、限界を迎えて意識を落とすことも中々出来ない。ゆめの中でだけでしか会うことが出来ないのに、それさえ碌に出来ないことがもどかしくて、苦しくて。
「だから、あいたいな。……貴方に」
貴方の旅の記憶を。いつかの子どもたちに話したような空の話を聞きたい。
これまでの旅路を、第二の生を、自分は彼に示せているだろうかと。祈るような気持ちできつく目を瞑ったその先に、網膜の裏に焼き付くようなあおいひかりが辺りに満ちて。その眩さに思わず腕で顔を覆えば――微かに笑うような誰かの気配がして、ラムネは恐る恐るに目を開きながら腕を下ろした。
「あ……、」
そこに居たのはうつくしき蒼銀の鱗を持つ巨大な竜であった。
ラムネの身の丈をゆうに越すその姿は厳かであり、それが彼の全盛期の姿なのだろうと一目で分かった。
『暫くぶりだね、ひとの子よ。……少し痩せたかね』
グル、と低い唸り声を上げながら鼻先を寄せて。軽く腕に触れた鱗の感触はすこしだけひやりとしていて、気遣うような声音はあの日と変わらぬやさしいもので、それがゆめまぼろしではないことを確かに感じさせてくれた。
「カエルム、さん」
震える声で名を呼べば頷く代わりにゆっくりと瞬いてくれる。ゆめのなかでは触れることさえ叶わないけれど、月が導いてくれた彼へとそっと手を伸ばせば目を伏せた竜はそれを受け入れてくれた。
抱き締めるには腕の長さが足りない。それくらいに竜はおおきくて。鼓動を喪ったはずの彼が今は静かに呼吸をしているのが抱き付いた今なら分かって、うれしくて、うれしくて。へへ、と微かに照れたように笑みを溢せば、竜も重ねるように笑ってくれているのを感じることが出来た。
「大好きだよ、カエルムさん」
いつもそばにいてくれて、守ってくれて、ありがとう。
ずっと伝えたかった言葉を確り意識を保っているうつつの世界で伝えられることが嬉しくて、ラムネは眩しげに目を細める。
『ありがとう。君が見せてくれる世界も、とてもきれいだ』
彼が自分をそう認めてくれたように、ラムネにとっても彼はかけがえのない友だった。
親愛なる竜。共にある|天《そら》。
「カエルムさんの話、聞きたいな」
貴方が辿った旅路を、その断片だけでもいい。もしも知ることが出来たならいつか共に巡りたいのだと。強請ればぐるぐると低く喉を鳴らすけれど、それが怒りの類ではないのだと直ぐに知る。
『であれば……白き翼たちを導いた話は如何か』
それは大地より溢れ出した悪意より住む場所を失った鳥のものがたり。
地を裂き、天は稲妻に割れ、すべてのいのちが魔の胎の中へと呑み込まれてしまったそのあとに。なんとか逃げ仰せた鳥たちがしくしくと岩礁で嘆いているのを、竜は気まぐれに旅の供と称して連れ出したのだと云う。
「……それで、鳥たちは?」
『新天地を見付けたのさ。此処ではない遠く……太陽に満ちたみどりの島にね』
幼い頃からずっとラムネは『兄』だった。
弟妹たちを支え、養い、育てていく過程で甘えられるものなどありはしなかった。けれど竜と話している今この瞬間だけは違う。寝しなに開いた冒険譚をひとり夢見た少年の日に――ほんの少しだけ、戻ることが出来るのだ。
●ちぐはぐなゆめものがたり
「成る程なぁ、システムに程近いのか君は」
人の想いに反応し、願いを叶える為だけのもの。
あおく輝くその様を眺め観ながら、ナギ・オルファンジア(■からの堕慧仔・h05496)は興味深げにみなそこに浮かぶ月を覗き込む。
「其れが在り方、君の望みであるならば、そのように致しましょうね」
それは扱い方に気を付けさえすれば善きもののままで居られる。人々に御伽話として語り継がれているのなら、きっとこの海域周辺に住まうひとびともまた『善きもの』なのだろう。
「そうだなぁ……翼の生えた魚や鱗のある兎。そういったあべこべのものは出せるかい?」
普通のお魚にはご挨拶しましたからね、なんて。ぱちりと片目を瞑って見せれば次にはへんてこないきものたちが周囲に溢れ出すのに、『あら素敵』とナギは目をぱちぱちと瞬かせた。
「ああでもナギは、普通の大きなわんちゃんもすきなので、そちらもお願いしようかな」
――ぼん!
一際大きな煙と共に現れたのは、立ち上がればナギの背丈を越してしまいそうな程のまっしろな雲――もとい、尻尾を千切れんばかりに振りながらおおきなしろい犬。
「まあ、まあ!」
右を向けばちいさな羽を羽ばたかせる魚。左を向けばひらひらとした尾鰭をくっつけた兎がくるりと宙を舞う。かと思えば『よそ見をしないで』とばかりに犬が飛びついてくるものだから、おかしくなって笑ってしまった。
「よし、おいかけっこでもしようか!」
言葉を解しているらしい動物たちは我先にと駆け出してナギのあとを懸命についてくる。彼らのつぶらな瞳の中に映るあおいろもまたうつくしく、海の中を空想上の動物たちと駆ける姿は実に|幻想的《メルヘン》だ。
「んふ。ふわふわ、みんな愛らしい」
いちばんに追い付いた犬の鼻先に軽く唇を触れさせれば、ぺろんと頬を舐められるのが少しばかりこそばゆい。
「君を通して、ブルー・ムーンに感謝を」
また逢おうねと微笑みかけたその先で。くしゃりと笑顔のかたちになった犬が、返事をするかのように『うぉん』と鳴いた。
●月下のレッド・ベリル
静謐の月はなにも語らず、穏やかにラデュレ・ディア(迷走Fable・h07529)をあおいひかりで包み込んでいた。
「これが、わだつみのブルー・ムーン……!」
人々に愛されたねがいといのりのかたちを見上げた少女の頬は淡く色付き、感嘆と共に漏れ出た声はその壮大さに知らず震えた。ただ静かにそこに御座す月を見詰めれば時を忘れてしまいそうなほどのこの世ならざる光景に思わず見惚れてしまう、けれど。
「…………?」
あおく輝く月のほど近くに人影が浮かんでいるような気がして、ラデュレは懸命にその姿を捉えようと目を凝らす。朧げなその輪郭は次第にはっきりとかたちを成し、ラデュレはそれが夜空の延長線であることを知る。
――女性、だろうか?
否、それは月下に咲く一輪のあかい花であった。
ドレスの裾がふわりと広がる様はまるで大輪の薔薇が咲いているかのよう。駆け上がる音階をなぞるようにくるくると、風に遊びながら彼女が身を翻すたびに絹糸のようなうつくしい白金の髪が月のひかりを受けて煌めきながら幾筋もの軌跡を描き出す。童話の中の姫君が描き出す演舞のような優美な姿を、ラデュレは己を包む景色がすっかり様相を変えていることさえ忘れて彼女を中心として広がる円舞曲を惚けたように見詰めていた。
くるり、くるり。あかいくつを軸にして、彼女が回る。回り続ける。
不意に。ほんとうにかみさまの気まぐれであるかのような、ほんの僅かの出来事だった。紫彩の瞳がこちらを向いて。一瞬。ほんの一瞬だけ、ぱちりと視線が交わった、気がして。
「(いま、目があった……?)」
赤薔薇の君のかんばせは、まるで自分と鏡合わせのようだと知る。否、ラデュレがもう少し齢を重ねて大人になったなら、彼女のような姿になるのだろうか。それほどまでに彼女の貌はラデュレと瓜二つで、それなのにその輪郭が記憶の何処にも存在しなくて。もう一度その姿を目に焼き付けようとするのに、彼女の姿は徐々に、徐々に遠ざかって行ってしまう。
「……待って。――待ってください……!」
くるり、くるり。薔薇の花弁が翻って、彼女は踊る。踊り続ける。
ラデュレの声は届かない。伸ばした手も、届かない。視線が交わったのは一度きり。遠く、遠く――やがて視界はあおく滲んで、ラデュレは自分がみなそこを揺蕩っていることを漸く思い出す。
「あれは……わたくしの、記憶……?」
潮に揺らいだ月だけがラデュレを黙したまま見下ろしている。
月が叶えてくれたのは、導いてくれたのは。ここではないいつか、何処かにあるはずの|祝祭《イースター》の|禁忌《しゅくふく》。確かにその目で見た筈なのに未だなにひとつも思い出すことは出来なかったけれど、それでもあれは確かに千切れた記憶、割れてしまった己が|殻《かけら》であったに違いない。
「……あのひとは、誰なのでしょうか」
わたくしの、何なのでしょうか。
幾つも浮かび上がる疑問に応える口を持つものはここにはいない。けれど、月の導きによって叶った奇跡はラデュレにとって喜ばしいものだったから。
今はただこのうつくしい月を見つめていたい。この目で見たものがまぼろしではなかったのだと忘れないように、確かめるように。少女の旅は未だはじまりを迎えたばかりで、落とした記憶のかけらたちは世界中に散らばっているのだと、月が教えてくれたから。
「また、素敵な出会いがありますように」
どうか。どうか。この先に続く路が、この月のようにあたたかなひかりに満ちていますように――少女の祈りをその裡に抱いて。月は静かに、みなそこをやさしく照らし続けていた。
●陽の残響
月よりも何よりも眩しい陽のひかりがあった。
「また半額の弁当買ってきたんですか」
『文句言うならやらんぞ』
「……まァ、食いますけど」
薄れぬままの声が耳を打つ。ああ、あの日こそが悪夢だったのではないだろうかと、夜鷹・芥(stray・h00864)は目前の太陽のいろを眩しげに見詰め返した。
『お前もそろそろ自炊のひとつ出来るようにならないとな。何度も言うようだが、コンビニ飯っつうのは存外――』
「アンタに言われたくないですよ」
まともに自炊をするようなら今こんな風に生温い弁当を並んで口に運んだりしてはいないだろうと。黙々と芥が作業のように米を咀嚼するのを面白がるかのように、■った男は芥の白米の領土へ一際大きな唐揚げを放り込む。
『肉好きだろ、沢山食って大きくなれよ』
まるで子どもにそうするかのように無邪気に告げるその言葉は、不思議と不快に感じなかった。油を吸った分厚い衣の唐揚げはお世辞にも美味いと言えるようなものではなかったが、それでもよかった。
アンタと食うから、味を感じることが出来たんだ。
芥がどうもと唐揚げと共に白米を頬張るのを見て、男はまた■う。■う――、――?
「……なあ、なんで、さっきから」
アンタの顔が、見えないんだ?
金木犀の色だけが眩しくて。香りだけがひどく強くて、目眩がした。
「(…………ああ、我ながら未練がましい)」
些細な日々だった。平凡ではなかったかもしれないが、それでも、芥の全てがそこにあった。安い半額弁当が何よりも美味かった筈なのに。ただそれだけのことが、今はこんなにも遠い。
ブルー・ムーン。倖せで残酷なひとときの夢。
けれど確かに、自分の中で残っているものを知ることが出来たから。
「……感謝を」
もしも。ひかりを失った旅路の中で再び巡り逢うことができたなら、その時は。
「(あなたの笑った顔が見れるだろうか)」
言葉は泡となって水面へと昇っていく。そのあえかなひかりを見上げ、芥は記憶の中の面影にそうするように柔く目を細めた。
●あめあがりのそのさきへ
ママとパパ。
もう、ずっと、あってないね。
元気でいますか? お仕事は大変ですか?
――さびしく、ないですか?
話したいことが、たくさんあった。ゆめの中でだって伝えたいことが、たくさん、たくさん。天深夜・慈雨(降り紡ぐ・h07194)はその細いからだが泡となって消えてしまわないように、きつく、きつく抱き締めて目を瞑る。
「あいたいよ」
ずっと、見つからない。
埋まらない。満たされない。悲しいよ。悲しいね。
大丈夫。全部雨が流してくれる。
――ほんとうに?
「……あいたい」
ぽっかりと胸に空いた『からっぽ』はどれだけ|あめ《あい》を注いでも満たされず、慈雨のこころにしとしととつめたい雫を降らせたまま。
ママ。パパ。あいたい。
ふたりはお仕事がいそがしいから、会えなくったって仕方ない。最後におはなししたのはいつだっけ。いつから、こう、なのだっけ。思い出せない。雨は止まない。でも、それでも。
「だけど……このおねがいは、自分で叶えたいなぁ」
自分の足で、自分のちからでふたりに会いに行って。『いっぱい頑張ったんだね』って、なつかしい声で、大きなてのひらで、いっぱい褒めて欲しいから。泣き虫な子どもは卒業したんだよって、安心させてあげたいから。
「だからね、水底のブルー・ムーン」
やさしく揺蕩うおつきさま。どんなねがいも叶えてくれるなら、どうか。
「この魔法みたいなあおの夜を、私は|この子《クロリス》ともっとずっと楽しみたい」
ずっとてのひらで大切に守ってきた一輪のあおい花。たった一夜しかいのちを紡げないこの子が、お友達と見ることが出来なかった景色を。
「この子と、一緒に!」
願いを抱いて。祈りに満ちて。やがて月はさらさらと消えていく。
月の残滓をいっぱいに浴びたクロリスの花が、刹那、一等星のように強く煌めく。
朝がくれば全てがうたかたのように消えてしまっても、慈雨のねがいは、いのりは消えない。あおいろの思い出をその身に宿し結晶へと姿を変えたクロリスが、少女のてのひらの中で確かに輝いていた。
